フットパス専門家講座泉の森の植物を訪ねて
2025.06.08
[講師:日本植物友の会会長山田 隆彦]
6月8日(日)天気:曇 参加者:13名
梅雨前の「泉の森」を訪ねた。小田急線の大和駅から歩け、気軽に散策できるのでこの地にはよく訪ねた。6月はキツリフネが咲きだす頃で、緑の林内にちらほらと咲きはじめていた。この稿では4種をとりあげようと思う。
ナガエミクリガマ科[長柄実栗]
水中で葉を流れに任せている植物、ナガエミクリといい、神奈川県では2か所でしか標本は採集されていない。花期以外の葉は水中にあり、沈水状態で過ごしている。本州~九州に分布しているが、水の流れていないところでは、ほとんど見られない。花期は6~9月、この地のものは、例年なら花穂を伸ばし咲きはじめているのであるが、今年は遅れている。ミクリ科という独立した科であったが、新しいAPG分類(DNAの分析にもとづく分類)ではガマ科となり、ミクリ科はなくなった。

 ナガエミクリ
ナガエミクリ
クマノミズキミズキ科[熊野水木]
ちょうど花盛りであった。白くこんもりと花がかたまりでつき、ミズキとそっくりであるが、花期が違う。クマノミズキはミズキより約1カ月遅く6~7月に咲く。名前は紀州熊野に産するミズキという意味。ミズキとの決定的な違いは、クマノミズキの葉は対生であるが、ミズキは互生である。また冬芽の形が違う。ミズキは鱗のような小さなかたい片に包まれた長い卵形であるが、クマノミズキは筆先のような形をしていて裸芽(芽鱗で覆われていない)である。

クマノミズキ
キツリフネツリフネソウ科[黄吊舟]
名前のとおり、花は黄色で姿はぶら下がった舟に似ている。学名(世界共通の名前)はインパチエンス・ノリタンゲレ(Impatiens noli-tangere)といい、属名のインパチエンスは「耐えられない」、種形容語のノリタンゲレは「触るな」という意味で、熟した果実を触れると突然はじけることによる。この辺りには、暗紅紫色のツリフネソウも分布している。花の色ですぐに分かる。それ以外にツリフネソウは葉の上に咲き、距(花の後ろにつく長い管)が渦巻状に巻いているが、キツリフネは葉の下に咲き、距は巻かないという違いがある。葉の形も違う。

キツリフネ
ノハカタカラクサツユクサ科[野博多唐草]
南アメリカ原産の帰化植物で、昭和初期に鑑賞用として葉に白い斑の入ったものが導入された。それが逃げ出し斑のないものが猛烈に増え、環境省の「要注意外来植物」に指定されている。この長い名前は、園芸種の葉の縞模様が博多織に似ていることから野に生える博多唐草と名付けられた。最近は別名のトキワツユクサの名を使う人が多くなった。

ノハカタカラクサ
種々の草花を楽しみながら、相鉄本線の相模大塚駅で解散した。
(文と写真:山田 隆彦)

植物に殆ど知識のない者として初めて大和を訪ね、泉の森観察会に参加させていただきました。山田先生のご説明から私が想像した事を拾い出してみます。
大和駅のプロムナードに真直ぐ伸びた並木があり、先生からメタセコイアと説明されました。メタセコイアは恐竜が栄えた白亜紀に出現した植物です。この並木が成長して30m程に高くなり恐竜が大和のメタセコイアの森を闊歩する風景を想像し、現代と白亜紀が錯綜したロマンを感じました。
次に植物の繁殖の工夫に関して。例えばツタのように伸びていく植物の場合、葉が茎から左右交互に周期的に出て、つるも規則正しく左右交互に出ています。太陽の光を満遍なく捉え且つ周りの植物等にうまく巻き付く為だそうです。またシダ植物の場合、仲間を増やすため、葉の裏に丸い小さな粒の集まりが並んでいます。時期が来ると粒がはじけて胞子が風に飛ばされ、地面に落ち繁殖するのだそうです。
上述の”花が咲かないシダ植物“は風が胞子を運んでくれるようです。一方、花が咲く植物には、風の力や、蜂、蝶、野鳥などが蜜を吸いに来て花粉を遠くまで運んでくれます。素人考えですが、後者の方が花粉の運搬量が多く広範囲で繁殖するので、花が咲かないシダ植物は羨ましがっているかもしれません。
ご説明の中に植物や人類の起源に関係する話も出て来ました。その中で、現存する被子植物でもっとも古いアンボレラという植物は、1億3000万年前の前期白亜紀に出現したと推定されているそうです。ここで恐竜の再登場です。植物の名前は中々頭に入って来なかったですが、ロマンをいただき有難うございます。
(文と写真:小田 直樹)

現実のメタセコイアの並木に恐竜を加えると
気軽に散策して、お目当ての植物を探す
6月8日(日)天気:曇 参加者:13名
梅雨前の「泉の森」を訪ねた。小田急線の大和駅から歩け、気軽に散策できるのでこの地にはよく訪ねた。6月はキツリフネが咲きだす頃で、緑の林内にちらほらと咲きはじめていた。この稿では4種をとりあげようと思う。
ナガエミクリガマ科[長柄実栗]
水中で葉を流れに任せている植物、ナガエミクリといい、神奈川県では2か所でしか標本は採集されていない。花期以外の葉は水中にあり、沈水状態で過ごしている。本州~九州に分布しているが、水の流れていないところでは、ほとんど見られない。花期は6~9月、この地のものは、例年なら花穂を伸ばし咲きはじめているのであるが、今年は遅れている。ミクリ科という独立した科であったが、新しいAPG分類(DNAの分析にもとづく分類)ではガマ科となり、ミクリ科はなくなった。

 ナガエミクリ
ナガエミクリクマノミズキミズキ科[熊野水木]
ちょうど花盛りであった。白くこんもりと花がかたまりでつき、ミズキとそっくりであるが、花期が違う。クマノミズキはミズキより約1カ月遅く6~7月に咲く。名前は紀州熊野に産するミズキという意味。ミズキとの決定的な違いは、クマノミズキの葉は対生であるが、ミズキは互生である。また冬芽の形が違う。ミズキは鱗のような小さなかたい片に包まれた長い卵形であるが、クマノミズキは筆先のような形をしていて裸芽(芽鱗で覆われていない)である。

クマノミズキ
キツリフネツリフネソウ科[黄吊舟]
名前のとおり、花は黄色で姿はぶら下がった舟に似ている。学名(世界共通の名前)はインパチエンス・ノリタンゲレ(Impatiens noli-tangere)といい、属名のインパチエンスは「耐えられない」、種形容語のノリタンゲレは「触るな」という意味で、熟した果実を触れると突然はじけることによる。この辺りには、暗紅紫色のツリフネソウも分布している。花の色ですぐに分かる。それ以外にツリフネソウは葉の上に咲き、距(花の後ろにつく長い管)が渦巻状に巻いているが、キツリフネは葉の下に咲き、距は巻かないという違いがある。葉の形も違う。

キツリフネ
ノハカタカラクサツユクサ科[野博多唐草]
南アメリカ原産の帰化植物で、昭和初期に鑑賞用として葉に白い斑の入ったものが導入された。それが逃げ出し斑のないものが猛烈に増え、環境省の「要注意外来植物」に指定されている。この長い名前は、園芸種の葉の縞模様が博多織に似ていることから野に生える博多唐草と名付けられた。最近は別名のトキワツユクサの名を使う人が多くなった。

ノハカタカラクサ
種々の草花を楽しみながら、相鉄本線の相模大塚駅で解散した。
(文と写真:山田 隆彦)

メタセコイアに、恐竜のいる白亜紀を想う
植物に殆ど知識のない者として初めて大和を訪ね、泉の森観察会に参加させていただきました。山田先生のご説明から私が想像した事を拾い出してみます。
大和駅のプロムナードに真直ぐ伸びた並木があり、先生からメタセコイアと説明されました。メタセコイアは恐竜が栄えた白亜紀に出現した植物です。この並木が成長して30m程に高くなり恐竜が大和のメタセコイアの森を闊歩する風景を想像し、現代と白亜紀が錯綜したロマンを感じました。
次に植物の繁殖の工夫に関して。例えばツタのように伸びていく植物の場合、葉が茎から左右交互に周期的に出て、つるも規則正しく左右交互に出ています。太陽の光を満遍なく捉え且つ周りの植物等にうまく巻き付く為だそうです。またシダ植物の場合、仲間を増やすため、葉の裏に丸い小さな粒の集まりが並んでいます。時期が来ると粒がはじけて胞子が風に飛ばされ、地面に落ち繁殖するのだそうです。
上述の”花が咲かないシダ植物“は風が胞子を運んでくれるようです。一方、花が咲く植物には、風の力や、蜂、蝶、野鳥などが蜜を吸いに来て花粉を遠くまで運んでくれます。素人考えですが、後者の方が花粉の運搬量が多く広範囲で繁殖するので、花が咲かないシダ植物は羨ましがっているかもしれません。
ご説明の中に植物や人類の起源に関係する話も出て来ました。その中で、現存する被子植物でもっとも古いアンボレラという植物は、1億3000万年前の前期白亜紀に出現したと推定されているそうです。ここで恐竜の再登場です。植物の名前は中々頭に入って来なかったですが、ロマンをいただき有難うございます。
(文と写真:小田 直樹)

現実のメタセコイアの並木に恐竜を加えると
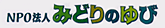
 2025.06.08 21:31
|
2025.06.08 21:31
| 


