フットパス専門家講座 東国(アヅマのくに)フットパス(その2)
2025.04.25
[ 講師:古街道研究家 宮田 太郎 ]
(縄文ロードと川尻遺跡編)
4月25日(金) 天気:晴 参加者:18名
テーマは、相模野の最奥部に位置する相模原市大島、川尻地区を「奥相模野」地域としてとらえ、そこに今も残る直線的な古街道が、実はおよそ数千年前の縄文時代に、多摩・町田と諏訪湖地方の高原地帯や八ヶ岳方面とを結びあった交流ルート=昨年黒曜石ロードだった?!――という壮大な歴史ロマンを胸に歩きました。
2千500年~6千年前の縄文時代に、長野県の高原地帯の山の民と、相模野・多摩丘陵・武蔵野の人々が、親戚のような交流を数千年も続けてきたなんて、現代ではなかなか想像できないことですが、このフットパスはそんなことを実感させてくれる小さな旅になったものと思います。
当日は暑さも予想されたため午後だけの開催とし、正午にJR橋本駅のミウィ前に集合。バスに乗って10数分ほどで下車した二本松の「八幡神社前」では、昭和40年の津久井湖ダム完成に先立って、昭和30年台後半にここへ移り住んだ約180世帯の集落(湖底に沈んだ荒川村などから神社や石仏をここに移した)であることを知りました。

八幡神社の石仏群
(写真:田邊)
その先は、旧津久井郡城山町と相模原市の境界線(古街道)に沿って段丘崖の森の中を下り、「古街道のゴールデンクロス」にあたるという地点を確認。

段丘崖の森の中を下る
その先では「津久井城跡」へと真っ直ぐに続く謎の古街道=縄文ロードをたどりました。

津久井城跡へ真っ直ぐに続く縄文ロード
オアシスのような大型スーパーで休憩後、「川尻中村遺跡」の跡地では、圧倒される量の出土物などを資料で確認。「新小倉橋」からの雄大な眺めを見たときは、相模川の川風が渡り、とても清清しい気持ちになりました。

長竹川尻線の上から、新小倉橋、城山と圏央道を見渡す


新小倉橋からの雄大な眺め相模川の小倉橋とリニア新幹線工事中の橋
橋を渡り対岸の「原東遺跡」を確認し、橋を戻って「川尻石器時代遺跡(国指定)」を探索。そこには石敷きの住居址が復元されており、また目前の「宝ヶ峰(津久井城跡)」の山頂には、冬至の太陽が沈むことも知りました。 これらの濃厚な縄文遺跡群は、まさに山脈を越えて黒曜石やヒスイ石を運んで来る八ヶ岳の縄文人たちが、往き帰りに休憩したり滞在していたベースキャンプではなかったかと想像させてくれます。

川尻石器時代遺跡の復元された石敷き住居址を観察
普段はあまり訪ねることもなく、観光地でもないこのエリアですが、まだまだ自然が豊富であり、遠い我々の祖先の逞しき暮らしが見えてくるようで、貴重な時間になったと思います。
( 文と写真:宮田 太郎)

新小倉橋より相模川の上流、神奈川県最古(昭和18年)の津久井発電所(写真:田邊)

国指定史跡川尻石器時代跡(写真:田邊)

川尻石器時代遺跡に参加者のみなさまと(写真:田邊)
土日が詰まっている私達にとってウイークデー開催のこの FP は願ってもなく、おかげで久しぶりに参加できました。それに数年前まで歩くのは体力維持が目的でしたが、最近は加えて歴史等の見聞が得られる行事に魅力を感じており、今回はまさにそういう企画でした。
川尻や小倉橋周辺は、以前、ゴルフや、宮ケ瀬ダムおよび丹沢の裏山などへ遊びに行くときに頻繁に通った所ですが、そこにこれほど大規模な遺跡群があることはまったく知りませんでした。
新小倉橋が開通した2004年以前は、相模川の向こう側へ行く場合、車は狭い(旧)小倉橋を対向車両がないことを確認して通行する、つまり交互通行のため時間がかかり、ここを通らなければ5~6㎞下流の高田橋まで迂回するしかなく、すごく不便な所だと感じていました。
その場所が、縄文時代には既に大集落があって多くの人が住んでいただろうこと、その後も黒曜石の運搬経路であった時代もあり、さらに相模の国や武蔵の国などと甲州方面を結ぶ主要な交通路の一つであっただろうこと等を知りました。黒曜石と聞き最初は何故かと思いましたが、刃物道具として使われた時代には重要な交易物だったのでしょうね。
現代のような通信手段・動力・機械等がなかった時代の人々は、どんな生活をしていたのだろうか?…住居や渡河手段等をどのようにして整備したのだろうか?…いろいろ想像するだけでロマンを感じます。
途中休憩した場所が、その遺跡群のある近くで、スーパーアルプスなどの店が入っているコピオ相模原インター店というモールでした。そのモールに立ち寄ったのも私達にとっては初めてでした。
宮田先生の詳細な資料と、広く深くとてもわかりやすいご説明で、大変面白く勉強になった一日でした。
(文:伊藤 英俊、民江)
奥相模の縄文大集落をフットパス
(縄文ロードと川尻遺跡編)
4月25日(金) 天気:晴 参加者:18名
テーマは、相模野の最奥部に位置する相模原市大島、川尻地区を「奥相模野」地域としてとらえ、そこに今も残る直線的な古街道が、実はおよそ数千年前の縄文時代に、多摩・町田と諏訪湖地方の高原地帯や八ヶ岳方面とを結びあった交流ルート=昨年黒曜石ロードだった?!――という壮大な歴史ロマンを胸に歩きました。
2千500年~6千年前の縄文時代に、長野県の高原地帯の山の民と、相模野・多摩丘陵・武蔵野の人々が、親戚のような交流を数千年も続けてきたなんて、現代ではなかなか想像できないことですが、このフットパスはそんなことを実感させてくれる小さな旅になったものと思います。
当日は暑さも予想されたため午後だけの開催とし、正午にJR橋本駅のミウィ前に集合。バスに乗って10数分ほどで下車した二本松の「八幡神社前」では、昭和40年の津久井湖ダム完成に先立って、昭和30年台後半にここへ移り住んだ約180世帯の集落(湖底に沈んだ荒川村などから神社や石仏をここに移した)であることを知りました。

八幡神社の石仏群
(写真:田邊)
その先は、旧津久井郡城山町と相模原市の境界線(古街道)に沿って段丘崖の森の中を下り、「古街道のゴールデンクロス」にあたるという地点を確認。

段丘崖の森の中を下る
その先では「津久井城跡」へと真っ直ぐに続く謎の古街道=縄文ロードをたどりました。

津久井城跡へ真っ直ぐに続く縄文ロード
オアシスのような大型スーパーで休憩後、「川尻中村遺跡」の跡地では、圧倒される量の出土物などを資料で確認。「新小倉橋」からの雄大な眺めを見たときは、相模川の川風が渡り、とても清清しい気持ちになりました。

長竹川尻線の上から、新小倉橋、城山と圏央道を見渡す


新小倉橋からの雄大な眺め相模川の小倉橋とリニア新幹線工事中の橋
橋を渡り対岸の「原東遺跡」を確認し、橋を戻って「川尻石器時代遺跡(国指定)」を探索。そこには石敷きの住居址が復元されており、また目前の「宝ヶ峰(津久井城跡)」の山頂には、冬至の太陽が沈むことも知りました。 これらの濃厚な縄文遺跡群は、まさに山脈を越えて黒曜石やヒスイ石を運んで来る八ヶ岳の縄文人たちが、往き帰りに休憩したり滞在していたベースキャンプではなかったかと想像させてくれます。

川尻石器時代遺跡の復元された石敷き住居址を観察
普段はあまり訪ねることもなく、観光地でもないこのエリアですが、まだまだ自然が豊富であり、遠い我々の祖先の逞しき暮らしが見えてくるようで、貴重な時間になったと思います。
( 文と写真:宮田 太郎)

新小倉橋より相模川の上流、神奈川県最古(昭和18年)の津久井発電所(写真:田邊)

国指定史跡川尻石器時代跡(写真:田邊)

川尻石器時代遺跡に参加者のみなさまと(写真:田邊)
アズマのくにフットパスに参加して
土日が詰まっている私達にとってウイークデー開催のこの FP は願ってもなく、おかげで久しぶりに参加できました。それに数年前まで歩くのは体力維持が目的でしたが、最近は加えて歴史等の見聞が得られる行事に魅力を感じており、今回はまさにそういう企画でした。
川尻や小倉橋周辺は、以前、ゴルフや、宮ケ瀬ダムおよび丹沢の裏山などへ遊びに行くときに頻繁に通った所ですが、そこにこれほど大規模な遺跡群があることはまったく知りませんでした。
新小倉橋が開通した2004年以前は、相模川の向こう側へ行く場合、車は狭い(旧)小倉橋を対向車両がないことを確認して通行する、つまり交互通行のため時間がかかり、ここを通らなければ5~6㎞下流の高田橋まで迂回するしかなく、すごく不便な所だと感じていました。
その場所が、縄文時代には既に大集落があって多くの人が住んでいただろうこと、その後も黒曜石の運搬経路であった時代もあり、さらに相模の国や武蔵の国などと甲州方面を結ぶ主要な交通路の一つであっただろうこと等を知りました。黒曜石と聞き最初は何故かと思いましたが、刃物道具として使われた時代には重要な交易物だったのでしょうね。
現代のような通信手段・動力・機械等がなかった時代の人々は、どんな生活をしていたのだろうか?…住居や渡河手段等をどのようにして整備したのだろうか?…いろいろ想像するだけでロマンを感じます。
途中休憩した場所が、その遺跡群のある近くで、スーパーアルプスなどの店が入っているコピオ相模原インター店というモールでした。そのモールに立ち寄ったのも私達にとっては初めてでした。
宮田先生の詳細な資料と、広く深くとてもわかりやすいご説明で、大変面白く勉強になった一日でした。
(文:伊藤 英俊、民江)
【緑地管理報告 4/20(日)】
2025.04.21
4月20日(日)10:00~11:30 くもり 参加者15名
20日は、本来はタケノコ祭りの日でしたが、天気予報では雨。
しかもタケノコが裏年で不作でもあり、タケノコ祭り(タケノコ汁)は中止になり、
タケノコを掘るだけになりました。
13日の生育調査では、5本しか掘れなかったのに、20日はなんと大小様々30本近く
収穫出来ました。昨年の肥料も効いたのでしょうか。
会員の方とご家族連れの初参加があり、楽しく賑やかな1日でした。
来週も穂先タケノコばかりでなくタケノコも掘れそうです。
昨年はずいぶん掘ったつもりですが、やはり新しい竹が何本も生えています。
成長した竹を伐採するのは一苦労です。
皆さんに穂先タケノコやタケノコのうちに収穫してもらえると、有難いです。
タケノコのあく抜きは、電子レンジで
10分の方法もあるようで、次はそれを試してみようと思います。
(記録 鈴木)
20日は、本来はタケノコ祭りの日でしたが、天気予報では雨。
しかもタケノコが裏年で不作でもあり、タケノコ祭り(タケノコ汁)は中止になり、
タケノコを掘るだけになりました。
13日の生育調査では、5本しか掘れなかったのに、20日はなんと大小様々30本近く
収穫出来ました。昨年の肥料も効いたのでしょうか。
会員の方とご家族連れの初参加があり、楽しく賑やかな1日でした。
来週も穂先タケノコばかりでなくタケノコも掘れそうです。
昨年はずいぶん掘ったつもりですが、やはり新しい竹が何本も生えています。
成長した竹を伐採するのは一苦労です。
皆さんに穂先タケノコやタケノコのうちに収穫してもらえると、有難いです。
タケノコのあく抜きは、電子レンジで
10分の方法もあるようで、次はそれを試してみようと思います。
(記録 鈴木)
【緑地管理報告 3/13(日)】
2025.04.14
4月13日(日)小雨 9時30分〜11時 参加者 6人
本日はタケノコの生育状態を調べるため雨が降り出す前、
いつもより早めに集まる。
竹林上の段で大小混ぜて数本をやっと掘ることができた。
ただ近くでは多数の掘られた形跡があった。
調査は不調でやはり今年はタケノコ収穫の裏年のようだ。
来週のタケノコ祭りの打合わせをする。
タケノコ祭り当日の天気、タケノコの不作のこと等勘案して
実施の可否を事務局で判断をすることにした。
竹林の春の花
スミレやタチツボスミレ、ヒトリシズカ、山椒(木ノ芽)等見つけられた。
昨年たくさんみつかっていたキンランがまだ見つからなく残念だった。
タケノコは不作でも竹林は「素晴らしい❣」が一杯です。
記録 新納
本日はタケノコの生育状態を調べるため雨が降り出す前、
いつもより早めに集まる。
竹林上の段で大小混ぜて数本をやっと掘ることができた。
ただ近くでは多数の掘られた形跡があった。
調査は不調でやはり今年はタケノコ収穫の裏年のようだ。
来週のタケノコ祭りの打合わせをする。
タケノコ祭り当日の天気、タケノコの不作のこと等勘案して
実施の可否を事務局で判断をすることにした。
竹林の春の花
スミレやタチツボスミレ、ヒトリシズカ、山椒(木ノ芽)等見つけられた。
昨年たくさんみつかっていたキンランがまだ見つからなく残念だった。
タケノコは不作でも竹林は「素晴らしい❣」が一杯です。
記録 新納
【緑地管理報告 3/23(日)】
2025.03.24
3月23日(日) 作業10:00~12:00 晴れ 参加者10名(含ゲスト3名)
打合せ12:30~14:30 小野路交流館 参加者 9名(内打合せのみ3名)
1) 竹林整備
·階段手摺設置
2か月前に取り掛かった下段への階段工事の仕上げとして、竹で手摺りを取り付けた。
登り降りが危ない下段との往来が、簡易ステップと簡易手摺りによって大幅に改善された。今後とも小まめにメンテすることにより、安心安全な往来に寄与すると期待される。
·草刈り実施
4月タケノコ祭りに備えて、人が集まる上段広場と下段竹林でアオキや雑草を刈り払った。広場には丸太スツールもあり、4月には賑やかなアウトドア·ランチが楽しめそう。
2) 筍祭り打合せ
·飲食準備
作業終了後に幹部3名が加わり、4月に開催するタケノコ祭りの事前打合せをした。
鍋、ヤカン、コンロ、ボンベ等の器具類の在庫状況と追加持ち込みについて確認した。食材については、手間は掛かるが安価かつ安心のため、従来どおり分担購入持込みとした。あとは安全な焚火が出来るよう、事前に柴木を準備して土穴も掘っておく予定。
·緑地看板整備
地図案内と注意書きポスターの基盤が薄い合板のため、風雨で破れ剥がれ落ちている。
新たに用意された透明アクリル板を基盤にして、再掲示する方針で準備を進める。
筍行事は会員/その同伴者が対象につき、公募ポスターの一部はテープ張りする。
(記録/写真: 合田)



打合せ12:30~14:30 小野路交流館 参加者 9名(内打合せのみ3名)
1) 竹林整備
·階段手摺設置
2か月前に取り掛かった下段への階段工事の仕上げとして、竹で手摺りを取り付けた。
登り降りが危ない下段との往来が、簡易ステップと簡易手摺りによって大幅に改善された。今後とも小まめにメンテすることにより、安心安全な往来に寄与すると期待される。
·草刈り実施
4月タケノコ祭りに備えて、人が集まる上段広場と下段竹林でアオキや雑草を刈り払った。広場には丸太スツールもあり、4月には賑やかなアウトドア·ランチが楽しめそう。
2) 筍祭り打合せ
·飲食準備
作業終了後に幹部3名が加わり、4月に開催するタケノコ祭りの事前打合せをした。
鍋、ヤカン、コンロ、ボンベ等の器具類の在庫状況と追加持ち込みについて確認した。食材については、手間は掛かるが安価かつ安心のため、従来どおり分担購入持込みとした。あとは安全な焚火が出来るよう、事前に柴木を準備して土穴も掘っておく予定。
·緑地看板整備
地図案内と注意書きポスターの基盤が薄い合板のため、風雨で破れ剥がれ落ちている。
新たに用意された透明アクリル板を基盤にして、再掲示する方針で準備を進める。
筍行事は会員/その同伴者が対象につき、公募ポスターの一部はテープ張りする。
(記録/写真: 合田)



フットパス専門家講座 東国(アヅマのくに)フットパス(その1)
2025.03.13
フットパス専門家講座東国(アヅマのくに)フットパス(その1)
[ 講師:古街道研究家 宮田 太郎 ]
相模川の「八景の棚」と、北条氏照娘・貞心尼が居た”環状集落&月見の丘”
3月13日(木) 天気:晴 参加者:14名
「アヅ(ズ)マの国のフットパス」の一環として、かつて相模国と呼ばれてきたエリアのうち、相模川の流れと、その段丘崖から湧き出す無数の湧水が造り出した小河川沿いの面白さをぜひ紹介したいと、早春の相模川の段丘崖周辺を歩くコースを設定しました。
当日はJR相模線の「下溝」駅に集合。近くの「八景の棚」の一角から雄大な相模川と丹沢の山々の眺めを楽しみ、「三段の滝(新旧二つ)」や「磯部の土塁」などを見ました。

三段の滝にて

相模川三段の滝近くの広場で(写真:田邊)
進むと、そこには戦国時代の小田原北条氏関連の「環濠集落(館城)」が、段丘下の低地に存在しています。珍しい中世武士の暮らしの痕跡です。



この集落は、台地からの湧水が集まってできた
保川(どうほがわ)をUの字型に屈曲させて、防衛も兼ねた島状地形を形成したものです。
そこは昔から「下溝堀ノ内」と呼ばれ、小田原北条氏の第4代目・氏政の弟,氏照(八王子滝山城、八王子の城主)が、娘の貞心尼のために、安全な環濠のある館城を築いた場所です。
この方の夫は有名な山中大炊助という武将だったのですが先立たれ、一人娘も失い、尼となって当地で過ごしたようです。30歳代後半で亡くなり、近くには菩提寺もあります。
興味深いのはお付きの武士たちの子孫がまだ環濠集落内や周辺に住んでおられることです。また、地元の人々から、今でも大変慕われているということです。
北条氏照は八王子のみならず、実は座間や海老名近くまで「由井領」という領地を持っていた可能性が高く、座間キャンプ辺りも「磯部城」という城の範囲ではないかと考えていますが、この辺りも「氏照領」だったことになります。
貞心尼さんを祀るお堂も環状集落の中にあり、参加者の皆さんと実際に堀の中を歩いてみました。
最後は段丘崖に今も残る古道を登って台地上のGIONスタジアムに出ました。そこには、伝説のとおり、貞心尼さんが二十三夜の月見をしたり、丹沢に沈む夕陽を眺めて暦を体感したりしたという小さな山があり、外周のランニングコースの中の小さな丘として今も存在していることがわかります。

段丘崖の古道を登る
最後は横浜水道上にある遊歩道(トロッコ道の解 説板あり)を、女子美大のバス停から各駅へと向かいながらの解散となりました。
(文と写真:宮田 太郎 )

大きく蛇行している相模川と段丘崖(写真 : 田邊)
貞心尼ゆかりの遺蹟に、地元の愛を感じて
今回のフットパスは橋本駅に集合し、そのまま相模線に乗車。下溝からスタートとなりました。当日は天気も良く、歩きやすいコンディションでした。今回は相模原市下溝を中心に、前半は相模川沿いの「八景の棚」の景色を楽しみ、後半は北条氏照の娘ゆかりの地を巡リました。
まず崖の上から相模川を見渡し、そのまま川に向かって降りて行きました。相模川に沿ってしばらく歩き、「三段の滝」を見て青空の下軽いお昼をとりました。
後半は歴史の舞台に進みます。相模川につながる鳩川・道保川沿いをゆっくりと歩き、古道を所々確認しながら、貞心尼の居住していた「環状集落跡」をぐるりと一周しました。貞心尼とは、戦国時代に小田原を中心に関東を領有していた北条氏照の娘だそうで、私は今回初めて知りました。現在の地図でも、ここだけうっすらと、過去の集落の痕跡のようなものがわかるところでした。そこから古道を移動しながら、家族を亡くした貞心が月を眺めていた「月見の丘」と、その碑を確認しました。
相模原の下溝地区には貞心尼ゆかりの神社や宝物などが残っており、地元の方に今でも愛されていることがよくわかるフットパスでした。
最後に、宮田さんのフットパスでの資料は枚数もさることながら、興味深い手書きコメントが多く読み応えがあり、それだけでも楽しめました。ありがとうございました。

貞心尼ゆかりの神社

宮田太郎先生
( 文と写真:太田 義博 )
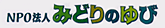
 2025.04.25 10:02
|
2025.04.25 10:02
| 


