[ 講師:日本植物学会副会長山田隆彦]
ちょっと珍しい植物園、秋の植物観察をしましょう
11月5日(土) 天気:晴参加者:5名
薬用植物園では、薬用植物だけではなく、園芸植物、野生植物、海外のものなど種々の植物が見られます。しかもほとんどに名札が簡単な説明とともに付けられているので、その植物のことを知ることができ有り難いです。写真を撮るときには、名札も別に撮っておくと、後の写真整理も楽にできます。
この植物園にはたくさんの種類が植えられており、一日中居てもあきません。今回の観察会でぜひ見ていただきたかったのはサフランです。サフランの花は赤い雌しべがとてもきれいです。これから黄色の色素をとり、染料や香料などに使われています。特に、古代ギリシャではサフランの黄色を珍重し、王族だけが使用できるロイヤルカラーとされていました。アヤメ科の植物で西南アジア原産です。ギリシャで最初に栽培されたと言われています。花期は10~12月で、橙赤色の三本に分かれた花柱が特徴です。よく似たものにイヌサフランがあります。「イヌ」がつくと役に立たないことを意味しますが、アルカロイドを含む毒草です。花期はサフランよりも1ヵ月早く9月ごろから咲きだし、赤い雌しべはありません。私たちが訪ねたときはすでに花は終わっていました。
サフラン
次に見て欲しかった植物はカンレンボク(旱蓮木)です。中国雲南省原産で、別名をキジュ(喜寿)といいおめでたい木として、喜寿になった方に記念で贈られるという話をよく聞きますが、大木になる木をいただいてもちょっと困ります。
訪ねた時は、ちょうど実がなっていて、その形はパイプウニに似ています。別な表現をすると、ごく小さなバナナの実が球状に集まった姿をしています。果実や根には抗がん作用の成分が見つかっているそうです。
カレンボクの実
この植物園が他の植物園と違うのは、法律で禁止されているケシの栽培をしていることです。医療用や研究用の栽培ですが、監視カメラが設置された厳重な二重の鉄柵の中で栽培されており、5月には色とりどりのケシの花を鉄格子の外から楽しめます。
ケシ栽培
菊の種類もいくつか植えられています。黄色の花のキクは、シマカンギクとキクタニギクです。シマカンギクは関西以西に分布し、キクタニギク(別名アワコガネギク)は本州と九州に分布します。葉の切れ込み方とか、頭花の大きさなどの違いがありますが、パッと見た目ではよほど慣れないと区別できません。中部地方以北で黄色の花の野生のキクはキクタニギクと見てよいです。

シマカンギク キクタニギク
リュウノウギクも満開でした。名札には、「民間療法で、冷え・神経痛・浅い外傷などに入浴剤として使用」とあります。このキクは、小野路などで簡単に見られます。
リュウノウギク
アカザ(下図)の茎が残っていました。アカザは老人の杖にするには、軽くて丈夫で最適です。水戸黄門もこれを使ったとか。名札には「若葉は食用になるが、多食すると日光皮膚炎を起こす」とあります。東京近辺では、アカザシロザのほうがずっと多くみられます。アカザの赤く見える部分は、粉状毛(水毛)といい、多くの水を含む細胞で、ここに赤い色素が入っているので赤く見えます。
野草園では、リンドウが満開でした。町田の里山や晩秋の山野で咲く最後の花です。「リンドウの花びらに見られる緑色の斑点に葉緑体があり、光合成を行っていることが発見されています」と、「みどりのゆび」で一昨年、小野路を案内した多田多恵子先生が『趣味の園芸』に書かれています。名前は漢方の「竜胆」からで、センブリと同様に苦味があり、健胃剤として用います。
リンドウ
帰りは「玉川上水」沿いに玉川上水駅まで、渓流沿いに生えている木々を楽しみながら散策しました。私も皆さまと一緒になって楽しみました。(文と写真:山田隆彦)
植物の観察にお勧めのユニークな植物園でした。
初めての訪問です。医薬品の原料となる薬用植物などを収集・栽培。ケシ・アサといった麻薬や危険ドラッグがとれる植物も試験栽培しているユニークな植物園です。身近な植物含め約500種の野生植物と1,500種の栽培植物。すべてタグ付、植物名と生薬としての名前、用途などが説明され、身近な植物にこんな用途があるのかと、読むのも楽しかったです。山田先生も、よく花の写真とタグを撮りにくるそうです。その後、山野草の写真などで「東京都薬用植物園」が撮影場所として記載されている記事が目につきました。
普段は、春の花を楽しんでいる植物も、秋に実をつけている様子を見ることができました。いつもは花を見るだけですが、今回、初めてびっしりと詰まったスミレのタネを見ました。
スミレのタネ
また、春に鮮やかな黄色い花が楽しみなサンシュユですが、秋には真っ赤な実でアキサンゴの別称も。民間療法では薬用酒にして強壮剤として利用。また、ナツメの実は、乾燥した果実は食材でもありますが、タイソウ(大棗)という生薬で、葛根湯や小柴胡湯など主要な漢方処方の構成生薬だそうです。林地では、黄色いヤクシソウの群生が見事でした。

サンシュユの赤い実 ヤクシソウの群落
( 文と写真: 田邊博仁)
[ 講師:高見澤邦郎]
ごく最近整備された大きな公園と100年前の震災後に整備された「浴風園」&烏山寺町を歩く
2022年10月1日(土) 天気:晴参加者:11名
秋のフットパス第1弾は快晴に恵まれた日の朝、井の頭線「浜田山」駅から出発。最初は数年前に開園された区立公園の探訪で、10分ほど歩き「柏の宮公園(4.3?)」に到着。元勧銀グラウンドを区が取得し、大きな公園として2004年に開園した。伸びやかな芝生にたくさんの家族連れが遊んでいました。そこを出て数分、「パークシティ浜田山」へ。三井不動産が2010年頃に開発したマンション群と戸建て住宅が広がる8.4?のエリアで、元は「三井上高井戸運動場」でした。区内で最も高価なマンション・戸建てでしょう。(皆さんの感想)「どんな人が住んでるんだろう」、「普段着じゃ出歩けないわね」とか。
修復保存された「三井倶楽部ハウス」
開発前の区や地元との協議で、昭和初期の“倶楽部ハウス”が修復活用されることに。室内には入れませんがテラスでは自由に休めます。その西にある「区立三井の森公園」もこの運動場の一部で、開発に伴って区が取得し、極力手を入れない自然保全型公園として2010年に開園されたもの。北に進むと「区立高井戸中学校」。昭和50年頃、『アンネの日記』を学び、アンネのバラのことも知った中学生たちが感想文を小冊子にまとめました。それをアンネの父親、オットー・フランクさんに送ったことがきっかけで3本の苗を送って貰えることに。以後、後輩たちが大事に受け継ぎ育て、春秋に美しく咲いています(ほんのちょっと咲き出したオレンジ色の花を見ることができた)。
次いで、「松本清張旧宅」を通り(清張さんのこと、小説のこと、会話が弾んだ)神田川沿いを歩き、井の頭線を渡って「杉並清掃工場」に到着。いわゆる東京ゴミ戦争を経て建てられた象徴的な施設です。騒動の経緯を展示するコーナーや焼却熱利用の足湯・プールも整備されています。さてこれで午前の部を終了。
井の頭線踏切から見る杉並清掃工場の煙突
午後の部はまず駅至近の「芝田山部屋(スイート親方!)」と「高井戸教会(外苑絵画館を設計した小林正紹による)」の前を通って「浴風園」へ。ここは関東大震災後の1925年、政府の肝入りで開設された日本で最初の公的高齢者施設で、今も残る本館・礼拝堂の設計は東大総長も務め安田講堂なども手がけた内田祥三が主導した。スクラッチタイル貼りの、強固な印象を与える建物です。広い園内には近年に建替えられた特養ホームや病院が並びますが、樹林も豊かな素晴らしい環境です(私もここに入りたいとの声アリ)。
本館を背景に記念撮影
病院西門から歩いて10分ほど、「都立高井戸公園」にたどり着きました。元はNHK・王子製紙・印刷局のグラウンドでしたが、都が取得し数年前に開園。震災等に備えた防災公園です(まだ整備中で完成時には20?ほどになる)。公園の西口からさらに10分ほど歩いて「玉川上水」に着きました。
今も流れる上水を中央に残しその左右に元からの桜並木がある緑道、さらに左右に各2車線の車の道路と歩道、住宅に面しては環境緩衝帯もある幅員60mの「東八道路久我山区間」で、長い地元との協議を経て最近開通しました。
広い草原、都立高井戸公園
さて緑道を少し歩いて左折10分、世田谷区に入って本日の最終目的地、烏山寺町に到着。ここには関東大震災後に下町(浅草、本所、芝など)から移ってきた26ヶ寺が並びます。代表的景観である「高源院」の鴨池を見て、あとは見たいお寺を各自でとして解散、京王線千歳烏山駅へと向かいました。
烏山寺町「高源院」の鴨池
あまり起伏がないとはいえ15kmほどを歩き少々くたびれましたが、バブル崩壊後の企業グラウンドが変身した大きな公園、「神田川」&「玉川上水」、そして震災の申し子の「浴風園」&寺町…。新旧の風景を体験しました。お疲れさま。
(文:高見澤邦郞写真:浅黄美彦)
ありたい「終の住処」を訪ねて
10月に入ったにも拘らず真夏日ほどの眩しい日差しの中、浜田山から高井戸、久我山の成熟した住宅街を粛々と歩いた一日でした。今回のルートを色で表現するなら、緑色。
10月なので新緑の〈笑う〉ではなく、ましてや中秋であっても〈粧う〉紅葉には時期尚早。それでも個人宅の庭木や生垣と、広々とした公園の芝生や木立、玉川上水沿いの緑道に茂った常緑樹などの緑の多さが、印象に残ります。
旧財閥のグラウンドも市民の憩いの場に
今回訪れた地域は、「環境遺産」とも言えます。明治から大正、昭和にかけて先人が取り組んだ、高齢者施設の「浴風園」や烏山寺町の一角、はたまた旧財閥が残した厚生グラウンドなどがレガシーとして、地域に引き継がれて来たことを再認識しました。(文と写真:蔵紀雄)
高井戸教会(写真:浅黄)
[ 四谷:江戸城外堀の内側は大名屋敷、外側は下級武士のまち] 今回は私の大学時代によく歩いた赤坂見附から四谷、四谷から新宿をご案内することにしました。このコースは、江戸城外堀を隔てて内側にあった紀伊徳川、尾張徳川、井伊彦根の江戸幕府中枢の大大名の屋敷町(紀尾井町)VS外堀の外側に広がっていた江戸城警護の下級武士の居住地区との対比がよくわかるところです。
四谷はその名の通りいくつも谷があり、典型的な「スリバチ」地形の底に花街や貧しい人達の住居もありました。屋敷町もスリバチ地域も江戸の名残がはっきり見られるとても楽しいコースです。

江戸切絵図紀尾井坂
出典:国立国会図書館、ROIS-DS人文学オープン
データ共同利用センター
[ ホテルニューオータニ:井伊家→伏見屋邸→大谷米太郎邸] 赤坂見附交番で集合。赤坂見附は江戸時代の見張りの城門で、弁慶橋を渡る時に見附跡が見えます。ここから四谷見附までが紀尾井町です。橋を渡った右側が、今は赤坂プリンスホテルから「東京ガーデンテラス」となった井伊邸の屋敷跡です。奥の庭園から清水が湧き出ていたことから付近は「清水谷」と呼ばれています。私たちは左側の井伊邸である「ホテルニューオータニ」に入り、エレベーターで5 階の日本庭園へ。戦後「伏見屋邸」をホテル創業者の大谷が買い取って、荒れ果てた庭を岩城亘太郎の設計の元に改修しました。1964年の東京オリンピックのために自邸をホテルニューオータニに建設し、日本庭園もホテルの一部となりました。
池泉回遊式で東屋や灯篭など多々ありますが、一番のおすすめは5階分に相当する高低差を活かした大滝です。

ニューオータニの大滝(写真:田邊)
5 階分上ってきたところに庭園があるため、立派な庭園を見た後はすぐ近くの出口から高低差なく四谷駅方面まで歩けます。この日は梅雨明け時の猛烈に暑い日だったのですが、お陰で気分よく次の目的地「上智大学」まで歩けました。上智生がデートにも使っている土塁の上のお堀端コースを正門まで歩きましたが、眼下には、地下鉄丸の内線が四谷で地上に出た時におなじみの、外堀を埋めたてたグラウンドが見えました。
[ 上智大学とクルトウラハイム:尾張徳川中屋敷から陸軍大臣高島鞆之助邸、そして上智学院へ]上智大学は日本初のカトリック教会系大学です。かのフランシスコ・ザビエルがローマと日本に大学を建学したいと述べてから数世紀を経た1911年、教皇は大学を設立するために3人の宣教師を送って「上智学院」を設立しました。そこで土地と建物が必要になり、井伊屋敷の後に居を構えた陸軍大臣高島鞆之助や隣地の陸軍大将大島久直らの邸宅が選ばれました。最初は大学をすぐ始められず「クルトウラハイム( 文化の家)」で社会人講座から始まりました。今でも高島邸であったクルトウラハイムは上智大学の中でも最古の明治時代からの建築物です。イエズス会が直に運営しており、今回は副館長のマイケル・ミルワード神父様に中をご案内いただくことができました。
[ クルトウラハイム:マイケル・ミルワード副館長のお話] 残念ながらクルトウラハイムの設計者はわかりません。1階は煉瓦作りですが、内装は日本風で暖炉の扉の絵などは日本画です。2階は木造で聖堂として使われており、上智出身者の結婚式やミサが行われています(ちなみに神谷もその一員です)。祭壇、後ろの屏風なども和風の金箔張りで、祭壇の真ん中に「SJ(Societas JIesuイエズス会)」と浮彫になっています。窓からは緑に囲まれた庭園が見え、都心とは思えない落ち着いた景色が広がっています。
最後に是非お見せしたい特別な部屋があります。スペインの美術史の専門家であった故神吉敬三教授が大塚国際美術館創設のプロジェクトとしてエル・グレコ衝立の復元に関わりました。そのモデルとして作成された縮小版を記念に贈られたのがこの部屋にあるもので、素晴らしいです。
(抜粋:神谷)

室内で神父にお話を聞く(写真:浅黄)
[ 聖イグナチオ教会から四谷見附へ] ミルワード副館長にお礼を述べ、一番古い建築物クルトウラハイムから、1932年に関東大震災後に再建された二番目に古い1号館へ。当時そのままの廊下を抜けて、正門の隣にある「聖イグナチオ教会」に向かいました。フランシスコ・ザビエルを派遣したイエズス会創始者のイグナチオ・ロヨラの名を取った教会です。1945年に建設された建物は、大きなステンドグラスに囲まれたヨーロッパ風の教会で好きでしたが、残念なことに老朽化で1999年に坂倉建築研究所の設計によって新教会が設立されました。和風な空間も取り入れモダンな建築になっています。

上智大学を背景に聖イグナチ教会にて(写真:田邊)
四谷見附の明らかな見附の跡を横目に、上智生のお気に入りと言われている「しんみち通り」で、選ぶのに困るほど種類の多いレストランから安くて美味しいランチを食べた後、名物「わかば」のたい焼きをお土産に買い、ルンルンと午後の外堀の外側、浅黄さんの「スリバチコース」に繋がりました。( 文:神谷由紀子)
スリバチの聖地・荒木町に大名屋敷跡地を巡る
午前中は外堀の内側、井伊家の「ホテルニューオータニ」、尾張家の「上智大学」を訪ねました。午後も引き続き、外堀の外側にある「美濃高須松平摂津守の屋敷跡」、スリバチの聖地でもある荒木町へ。大名屋敷跡地を巡るフットパスコースとなりました。
尾根道の甲州街道沿いの町家から少し入ったところは、かつての旗本屋敷があった場所。明治になって屋敷の真ん中に路地が通され、町屋と長屋が作られ、現在も路地の両側に飲み屋と住宅が残って江戸の町割を感じさせるエリアでもあります。
高台にある江戸からの古い道を進むと、途中に谷へ下る大階段がある。最初に出合った階段は下らず、まずは荒木町の高台の縁を回り、すり鉢の大きさを確かめながら少しずつ下っていくのが、荒木町を味わうコツという。

荒木町の路地
高台にある江戸からの古い道を進むと、途中に谷へ下る大階段がある。最初に出合った階段は下らず、まずは荒木町の高台の縁を回り、すり鉢の大きさを確かめながら少しずつ下っていくのが、荒木町を味わうコツという。
「金丸稲荷神社」前の風情ある路地を進み、「津の守弁財天」を擁する「策(むち)の池」に下っていくと、途中には料亭がある。そこからすり鉢をぐるりと一周すると池の底にたどりつきます。今は滝壺跡に水底がわずかに残るのみですが、想像の世界を膨らませ四方を囲まれた1級スリバチの地を堪能しました。

策(むち)の池
真夏のような炎天下ゆえ、細道を10分ほど歩き左門町の「於岩稲荷」・「田宮神社」をお参りすると、さすがにぐったりしてきます。斜向かいにある「陽運寺」境内でかき氷をいただき、のんびりと夏バージョンのフットパスコースを楽しみました。

( 文と写真:浅黄美彦)
小田急線の地下化は2013年に完成し、その後線路跡地(地上部)のまちづくりが進められ、2022年「下北線路街」として、世田谷代田駅から東北沢駅まで約1.7キロの整備が完了しました。今回のフットパスでは、この下北線路街の新たなまちづくりを見ながら、かつての小田急線沿線風景、例えば「代田小学校」、環状7号線、スポーツジム、映画館、「金子ボクシングジム」などの記憶を重ね楽しんでみようというのが一つ目の目的です。二つ目は、代々木八幡駅から、元代々木、西原あたりの高級住宅地に点在する建築家(吉阪隆正、横河健、槇文彦、清家清など)の設計した住宅を訪ね、戦前からの郊外住宅地の熟成のようすを眺めてきました。
昨年からのフットパス専門家講座では、小田急沿線の小田原、伊勢原丘陵、座間、玉川学園、生田、成城学園と歩いてきました。今回のコースを含めると、おおよそ小田急小田原線を踏破したような感じになります。

ダイダラボッチの足跡広場(世田谷代田駅前広場)
世田谷代田駅前広場から「下北線路街」の西端にある「代田富士356(みごろ)広場」の間は、遊歩道で結ばれています。その沿道には地域複合施設「世田谷代田キャンパス」、賃貸住宅「リージア代田テラス」、店舗兼事務所「カルディノ」など、このまちに必要な施設が丹念に読み込まれ配置されているような印象を受けました。特に東京農大が運営する「農の蔵」は、醸造学科のOBが手掛けた日本酒が常備され、時折訪れたくなる店になりそうです。

農大世田谷代田駅前キャンパス
「代田富士356広場」から東へ戻り、世田谷代田駅前を過ぎると温泉旅館「由縁別邸代田」がある。近くには旧家と「白髭のシュークリーム工房」があり、遊歩道の緑と相まってリゾート地にいるような気分を味わえます。

由縁別邸代田
さらに東へ歩くと幼保園、その先に店舗兼用住宅4棟と商業棟からなる新しいスタイルの商店街「ボーナストラック」があります。敷地中央にある共用の庭には、各店舗が自由に家具やサインを設置した、イベント空間にもなる素敵な空間で小休止。かつて、線路で分断されていた密集市街地を繋ぎながら、そこにあったらいいなと思える施設や空間が配置されています。

ボーナストラック
「ボーナストラック」から鎌倉道を横切り坂道を下ると、ギャラリーやシモキタ園芸部「ののこや」が見える。野趣あふれる植栽空間が気持ちがよい。飲食店街がある「シモキタエキウエ」、駅前市場があった下北沢駅東口の暫定空間を通り過ぎ、「オーゼキ」、「本多劇場」、「あずま通り」という下北らしい細道を抜けると「ザ・スズナリ」が見えます。1981年に下北に最初に開場した小劇場。翌年には「本多劇場」がオープンします。

ザ・スズナリ
「ザ・スズナリ」の背後に「カトリック世田谷教会」がある。ロマネスク風の木造の教会堂と手作りのルルド、カマボコ兵舎を転用したかつての信徒館など、信者でなくとも思わず祈りたくなるような空間がそこにあります。

カトリック世田谷教会
下北沢でそれぞれ食事し、代々木八幡駅へ。午後の部は、元代々木、西原、上原あたりの高級住宅地を歩きました。駅前の崖上には横河健氏設計のトンネル住居と「ザ・ツイスト」、「代々木八幡神社」にお詣りし、吉阪隆正氏の「ヴィラ・クゥクゥ」、篠原一男、清家清など、巨匠の住宅を眺め、代々木上原駅にたどり着いて解散しました。
( 写真と文:浅黄美彦)

代々木八幡神社(写真:田邊)
小路と植栽が繋ぐ新しい街の魅力
午前中は「下北線路街」を、午後からは代々木上原近辺のハイソな住宅街を歩きました。またじっくり訪ねたいと思える歩き甲斐のある充実したコースでした。当日の暑さのおかげで帰り際に寄った打ち上げビールが美味しかったこと!
私からは、特に印象深い「ボーナストラック」について報告します。世田谷代田から東北沢あたり、小田急線の地下化に伴ってできた「下北線路街」。特に、世田谷代田駅周辺が素敵でした。それぞれに街へのコンセプトを感じる「農大世田谷代田駅前キャンパス」、賃貸テラスハウス、駅前保育園、温泉旅館、茶房や料亭、そして、「ボーナストラック」。ボーナストラックは、賃貸価格を抑えて若い人たちが住みながら商いの冒険もしやすいように企画されたのだそうです。なるほど建築は超ローコストですが、お店のエリアを区切らないオープンな小路と建物配置、植栽の外構計画が素晴らしい。最近はランドスケープにお金をかけた計画が目立ちますね。憧れのリンデンバウムの木(しかも株立ち)とリンデンバウムの花を初めて見ました!

そして、ただのオシャレな街区とは違う文化的?なお店が集まっていて、多くの人を引き寄せています。(セレクト本屋は是非また行きたいです!) 「下北線路街」を魅力的にしているもう一つの要素が、車が入らない街路をナチュラルで涼しげな植栽が各施設を柔らかく魅力的に繋いでいることです。従来の日本ではないような。でも、どこの国とも違う。新しい街の景色として広がったらいいなぁと、小路と植栽の力を改めて感じました。( 文と写真:木村真理子)
他のまちのフットパスをみてみよう 粋な文化と情緒の残る牛込神楽坂
[ 講師:田邊博仁]
江戸の道、漱石の散歩道、石畳と黒塀の横丁を歩き、
牛込神楽坂の歴史に触れる
地下鉄牛込柳町駅からスタート。幸国寺へ移築した田安徳川家の山門を見て、「新宿区立早稲田小学校」の道へ。関東大震災後の復興事業の素敵な建物(昭和3年)で、今も使われている。現在の耐震水準でも問題ないそうです

震災復興当時の校舎の早稲田小学校
「漱石山房通り」を進むと「漱石公園」と「漱石山房記念館」に出ます。漱石が亡くなるまでの9年間を過ごした所で、関連書籍や資料の展示、猫塚があります。漱石山房記念館内に漱石の書斎が再現され、ここで、『三四郎』『それから』『こころ』などの代表作が執筆されました。

漱石山房記念館横の漱石公園
早稲田通りと並行する東側の昔ながらの小径(奥神楽坂)がいいです。手作りで評判のおはぎ屋、赤城神社の手前にかわいらしい一軒家の小さな「ドーナツ屋」があります。食べ歩きを楽しみました。

かわいらしい一軒家のドーナツ屋さん
赤城坂から北の参道を登り、牛込の総鎮守「赤城神社」へお参りしました。再生プロジェクト(隈研吾監修、2010年完成)により建替えられた新しい神社です。

本日の参加者と赤城神社
「ラ・カグ」の「AKOMEYA TOKYO神楽坂」で、ランチタイムです。
午後は、矢来町の「古今亭志ん朝旧宅」、文化財の「一水寮」・「鈴木家住宅」、「最高裁判所長官宅」や「尾崎紅葉旧居跡」などを見て回り、いわゆる“神楽坂界隈”へ出ました。
「熱海湯」、その横の「熱海湯階段(芸者小路とも)」を登ると見番へ抜け出られます。狭いですが素敵なお店が並んでいます。この坂を“フランス坂“と名付けたパリジェンヌ
(ドラ・トーザン)がいますよ。

熱海湯階段(芸者小路、フランス坂とも)
「毘沙門天・善國寺」にお参りして、「寺内公園」へ。ここは、鎌倉時代からあった「行元寺」の跡地の公園です。江戸時代には寺の境内が町屋や遊興の場所として賑わい、神楽坂の花街の発祥の地です。

神楽坂花街の発祥の地寺内公園
「兵庫横丁」へもどると、「ホン書き旅館」として有名な旅館「和可菜」があります。わずか4部屋ですが、多くの文豪が利用し、山田洋次の『男はつらいよ』もここで書かれました。
2016年閉店となっていましたが、隈研吾らによって今年(2022年)再生されます。

兵庫横丁とホン書き旅館・和可菜

酔石横丁と伊勢藤
牛込神楽坂
江戸時代の武士の居住地から庶民の遊び場へと歩く楽しみの多いコースである。古い町割りが今も残っていると聞いている。古い道や路地は入り込んでみるとそこはタイムマシンでありワンダーランドでもある。時代や時の流れが沈潜していたり、生活の積み重ねが露呈している。
私の目当ては神楽坂界隈。外堀通りから「庾嶺坂」を上り「小栗横丁」へ入る。変哲もない路地だけどいわゆる神楽坂らしい雰囲気が漂っている。路地中程の銭湯「熱海湯」の脇から「芸者小路」・「熱海湯階段」を上り「見番横丁」で見番を見学、「神楽坂通り」に出て「善国寺・毘沙門天」をお参り。いよいよ神楽坂散策の核心部へ。「行元寺」跡の高層マンションに囲まれた小さな「寺内公園」から界隈で最も古い道、鎌倉古道の石畳の「兵庫横丁」、福井藩家老の本多家の屋敷のあった神楽坂で一番大きな「本多横丁」、花柳界の雰囲気が残っている石畳の「かくれんぼ横丁」を経て「神楽坂仲通り」、神楽坂そして飯田橋駅へ。
花も実もある横丁歩き、思いっきり楽しかった。
居酒屋の「伊勢藤」の横を通ったが、ここは東京三大飲み屋の一軒。他は鶯谷の「鍵屋」、大塚の「江戸一」だが、最近はミシュランに湯島の「シンスケ」が載ったことから「伊勢藤」に代わり「シンスケ」を挙げる向きもある。
( 文:岩﨑英邦)
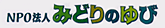
 2022.11.05 12:00
|
2022.11.05 12:00
| 


