フットパス専門家講座 阿佐ヶ谷から西永福町までを歩く
2024.11.09
[ 講師: 浅黄 美彦 ]
武蔵野に象徴される東京の郊外を探訪
11月9日(土) 天気:晴 参加者:23名
阿佐ヶ谷といえば中央線沿線の代表的な郊外住宅地であり、文士が住み名画座がありながら、北口の飲み屋街、パールセンターなど古い商店街がある様々な顔をもつまちです。今回の阿佐ヶ谷フットパスでは、そうした阿佐ヶ谷らしい場所も通りつつ、「武蔵野に象徴される東京の郊外を川・古道・神社・商店街など」をチェックポイントに、武蔵野の原風景(古層)も訪ねてみました。JR中央線阿佐ヶ谷駅南口に集合。ざっとコースのアウトラインを説明し、まずは駅から見える「中杉通り」と「阿佐ヶ谷パールセンター」という新旧の道を眺めてみました。
戦後すぐ、青梅街道から阿佐ヶ谷駅をまっすぐに結ぶ都市計画道路と並行した古道にある阿佐ヶ谷パールセンター。東京都初の歩行者専用道指定されたアーケード商店街は、中杉道路があってこその人のための道として栄えたようです。新旧の道が支え合ってまちの魅力となっている稀有な事例でもあります。その古道を北へ少し歩くと、かつてのケヤキ屋敷を抜け、阿佐ヶ谷神明宮を訪ねました。村々を結ぶ古道は、集落の道と繋がり、旧家と神社のある村の構造を垣間見せてくれます。

阿佐ヶ谷パールセンター

中杉通りのケヤキ並木
阿佐ヶ谷の総鎮守から南へ歩き、古本屋のある小さなアーケード、飲み屋街の細道を抜け、名画座「ラピュタ阿佐ヶ谷」を訪ね、再び阿佐ヶ谷パールセンターへ。少し曲がった道の商店街には道祖神もあり、この道が古い道であることを教えてくれます。

阿佐ヶ谷神明宮にて参加者のみなさまと
(写真:田邊)
青梅街道を横切り、戦前からの郊外住宅地にある「ドーモ・アラベスカ」へ。参加者の山本さんの計らいとオーナーの富田さんのご好意により、住宅の内部を見ることができました。

ドーモ・アラベスカ外観
富田玲子さん設計の素敵な住宅をあとに、緩やかな坂を下ると旧阿佐ヶ谷住宅跡地に出ます。現在は高級マンションが建っています。日本住宅公団のエース津端修一と前川國男事務所の大高正人らによる珠玉のテラスハウスが集合する団地で、そのありようを語りながら善福寺川に向かいました。

かつての阿佐ヶ谷団地
ここからは善福寺川沿いの気持ちのいい道を南に歩きます。この心地よい空間は、戦前の風致地区指定、昭和30年代初めの都市計画緑地・公園の決定など、都市計画の成果のひとつでもあります。その公園内にある「孤独のグルメ」でも登場した釣り堀のある食堂「武蔵野園」で昼食としました。

武蔵野園
昼食後はのんびりとさらに川沿いを下り、杉並博物館へ。ここはかつての嵯峨侯爵別邸、愛新覚羅浩はこの場所から結婚式場となる九段会館までパレードした歴史ある地でもあります。緑濃い善福寺川の周辺は、戦前富裕者の別邸が点在していた場所であったことを教えてくれます。

杉並博物館にて集合写真(写真:田邊)
いよいよ最後の目的地、大宮八幡宮へ。このあたりは、善福寺川沿いの緑地と特別緑地保全地区に指定されている神社の緑地が折り重なり、深い森のように見えます。中央線阿佐ヶ谷駅近くの阿佐ヶ谷八幡宮から、古道と川沿いを歩いていただき、井の頭線西永福町駅近くの大宮八幡宮というルートで、ちょっと変わった杉並の姿を見ていただきました。

善福寺川と緑地

大宮八幡宮
(文と写真:浅黄 美彦)
憧れのドーモ・アラベスカに感動!
私はかつて、吉祥寺と西荻窪からほど近い東京女子大学に通っていたので、杉並の中でも西荻は馴染みのあるまちでした。しかし阿佐ヶ谷は未開拓。阿佐ヶ谷でぱっと思いつくのは「阿佐ヶ谷姉妹」くらいでした(笑)。とはいえ 2024 年はミニシアター「ポレポレ東中野」で、杉並区に岸本聡子区長が誕生するまでの映画「映画◯月◯日、区長になる女。」を観た こともあり、私にとって杉並は23 区の中で胸熱なまち!・・・というわけで、「N P O法人みどりのゆび」の案内チラシを拝見し、ぜひにと「阿佐ヶ谷フットパス」に申し込みました。
お天気にも恵まれ、充実の阿佐ヶ谷探訪に大満足でした。開催日の 11 月 9 日は七五三撮影の最盛期だったようで、阿佐ヶ谷神明宮は晴れ着を着た家族でいっぱい。みなさん一様に晴れやかな顔で、私も幸せのお裾分けをいただきました。賑やかな商店街を抜け、住宅地に入ると細い路地の両側には「道路拡幅反対」ののぼり旗が。
「おお、この道が青梅街道から五日市街道までの事業予定区間である補助 133 号線なのか」と映画のロケ地を巡っているような気持ちにもなりました。その後は、内覧を楽しみにしていた象設計集団、富田玲子さんのご実家ドーモ・アラベスカ(現・高橋邸)へ。富田さんは東大の建築学科第1号の女子学生だったそうで、憧れと共に玄関をくぐりました。
1974 年に建てられたという洞窟のような家には、多彩な蔵書や美術品、可愛らしいキッチン雑貨がギュギュッと詰まっていて、日常と非日常が渾然一体となったインテリアに直接触れられることにも感動しました。「床暖房はとっくの昔に壊れちゃって、冬は寒くて大変ですよ」とジョーク混じりに話す、富田さんの息子さんのお家解説も楽しかったです。

ドーモ・アラベスク内部
(文と写真:宇野津 暢子)
武蔵野に象徴される東京の郊外を探訪
11月9日(土) 天気:晴 参加者:23名
阿佐ヶ谷といえば中央線沿線の代表的な郊外住宅地であり、文士が住み名画座がありながら、北口の飲み屋街、パールセンターなど古い商店街がある様々な顔をもつまちです。今回の阿佐ヶ谷フットパスでは、そうした阿佐ヶ谷らしい場所も通りつつ、「武蔵野に象徴される東京の郊外を川・古道・神社・商店街など」をチェックポイントに、武蔵野の原風景(古層)も訪ねてみました。JR中央線阿佐ヶ谷駅南口に集合。ざっとコースのアウトラインを説明し、まずは駅から見える「中杉通り」と「阿佐ヶ谷パールセンター」という新旧の道を眺めてみました。
戦後すぐ、青梅街道から阿佐ヶ谷駅をまっすぐに結ぶ都市計画道路と並行した古道にある阿佐ヶ谷パールセンター。東京都初の歩行者専用道指定されたアーケード商店街は、中杉道路があってこその人のための道として栄えたようです。新旧の道が支え合ってまちの魅力となっている稀有な事例でもあります。その古道を北へ少し歩くと、かつてのケヤキ屋敷を抜け、阿佐ヶ谷神明宮を訪ねました。村々を結ぶ古道は、集落の道と繋がり、旧家と神社のある村の構造を垣間見せてくれます。

阿佐ヶ谷パールセンター

中杉通りのケヤキ並木
阿佐ヶ谷の総鎮守から南へ歩き、古本屋のある小さなアーケード、飲み屋街の細道を抜け、名画座「ラピュタ阿佐ヶ谷」を訪ね、再び阿佐ヶ谷パールセンターへ。少し曲がった道の商店街には道祖神もあり、この道が古い道であることを教えてくれます。

阿佐ヶ谷神明宮にて参加者のみなさまと
(写真:田邊)
青梅街道を横切り、戦前からの郊外住宅地にある「ドーモ・アラベスカ」へ。参加者の山本さんの計らいとオーナーの富田さんのご好意により、住宅の内部を見ることができました。

ドーモ・アラベスカ外観
富田玲子さん設計の素敵な住宅をあとに、緩やかな坂を下ると旧阿佐ヶ谷住宅跡地に出ます。現在は高級マンションが建っています。日本住宅公団のエース津端修一と前川國男事務所の大高正人らによる珠玉のテラスハウスが集合する団地で、そのありようを語りながら善福寺川に向かいました。

かつての阿佐ヶ谷団地
ここからは善福寺川沿いの気持ちのいい道を南に歩きます。この心地よい空間は、戦前の風致地区指定、昭和30年代初めの都市計画緑地・公園の決定など、都市計画の成果のひとつでもあります。その公園内にある「孤独のグルメ」でも登場した釣り堀のある食堂「武蔵野園」で昼食としました。

武蔵野園
昼食後はのんびりとさらに川沿いを下り、杉並博物館へ。ここはかつての嵯峨侯爵別邸、愛新覚羅浩はこの場所から結婚式場となる九段会館までパレードした歴史ある地でもあります。緑濃い善福寺川の周辺は、戦前富裕者の別邸が点在していた場所であったことを教えてくれます。

杉並博物館にて集合写真(写真:田邊)
いよいよ最後の目的地、大宮八幡宮へ。このあたりは、善福寺川沿いの緑地と特別緑地保全地区に指定されている神社の緑地が折り重なり、深い森のように見えます。中央線阿佐ヶ谷駅近くの阿佐ヶ谷八幡宮から、古道と川沿いを歩いていただき、井の頭線西永福町駅近くの大宮八幡宮というルートで、ちょっと変わった杉並の姿を見ていただきました。

善福寺川と緑地

大宮八幡宮
(文と写真:浅黄 美彦)
憧れのドーモ・アラベスカに感動!
私はかつて、吉祥寺と西荻窪からほど近い東京女子大学に通っていたので、杉並の中でも西荻は馴染みのあるまちでした。しかし阿佐ヶ谷は未開拓。阿佐ヶ谷でぱっと思いつくのは「阿佐ヶ谷姉妹」くらいでした(笑)。とはいえ 2024 年はミニシアター「ポレポレ東中野」で、杉並区に岸本聡子区長が誕生するまでの映画「映画◯月◯日、区長になる女。」を観た こともあり、私にとって杉並は23 区の中で胸熱なまち!・・・というわけで、「N P O法人みどりのゆび」の案内チラシを拝見し、ぜひにと「阿佐ヶ谷フットパス」に申し込みました。
お天気にも恵まれ、充実の阿佐ヶ谷探訪に大満足でした。開催日の 11 月 9 日は七五三撮影の最盛期だったようで、阿佐ヶ谷神明宮は晴れ着を着た家族でいっぱい。みなさん一様に晴れやかな顔で、私も幸せのお裾分けをいただきました。賑やかな商店街を抜け、住宅地に入ると細い路地の両側には「道路拡幅反対」ののぼり旗が。
「おお、この道が青梅街道から五日市街道までの事業予定区間である補助 133 号線なのか」と映画のロケ地を巡っているような気持ちにもなりました。その後は、内覧を楽しみにしていた象設計集団、富田玲子さんのご実家ドーモ・アラベスカ(現・高橋邸)へ。富田さんは東大の建築学科第1号の女子学生だったそうで、憧れと共に玄関をくぐりました。
1974 年に建てられたという洞窟のような家には、多彩な蔵書や美術品、可愛らしいキッチン雑貨がギュギュッと詰まっていて、日常と非日常が渾然一体となったインテリアに直接触れられることにも感動しました。「床暖房はとっくの昔に壊れちゃって、冬は寒くて大変ですよ」とジョーク混じりに話す、富田さんの息子さんのお家解説も楽しかったです。

ドーモ・アラベスク内部
(文と写真:宇野津 暢子)
他のまちのフットパスをみてみよう 江戸下町情緒が残る「谷根千」の“今“を歩く
2024.11.07
[ 講師:田邊 博仁 ]
11 月7日(土) 天気:快晴 参加者:13名
根津は、根津神社の門前町として栄え、庶民のまちとして賑わってきました。江戸時代の町割りを継承している路地、木造の建物や軒先などに溢れる緑など、むかしの古き良き佇まいを残し、懐かしさを感じさせます。歩いていてホッとする空間です。

元藍染川(区境)の路地

路地のゲストハウス

古民家の「花木屋」

三軒長屋の古民家店舗
また、根津には古民家を改築した建物が多い。大正初期の木造三階建て建物を改築した「はん亭」、明治の古いレンガ造りの蔵を改装した「うどん釜竹」、また、緑に囲まれた路地のゲストハウス、「花木屋」や三軒長屋の古民家店舗、廃業した銭湯をリニューアルした「SENTO」などを見て歩きました。

古い蔵を保存「うどん釜竹」

銭湯を再整備した「SENTO」
次に、不忍通りを渡り、大正8年に建てられ、関東大震災でも東京大空襲でも焼けなかった根津教会、根津遊郭の跡地のモニュメントを見て、根津神社へ向かいました。
根津神社の創建は1706年。当時の建物は現存して、修復作業が行われた極彩色の美しい楼門などは見事です。青空には大イチョウが鮮やかでした。

日本基督教団根津教会

極彩色の桜門

境内の鮮やかなイチョウの木

根津神社の桜門をバックに、本日の参加者のみなさま
再び不忍通りを渡り、へび道、よみせ通りをぶらぶら歩き、谷中ぎんざ界隈で昼食です。

谷中ぎんざ(写真:宇佐美)
午後は、築約100年の日本家屋をリノベーションした建物(「錻力屋」、「銅菊」、「小倉屋質店」)、江戸時代の「観音寺築地塀」や「絵馬堂」、「のんびりや」、古書「鮫の歯」などを見ながら、谷中霊園へ。参道の明治からの老舗花屋「花重」に「花重谷中茶屋」がオープン(2023年)していました。

絵馬堂(休業中)

古書「鮫の歯」
そして、昭和13年に建てられた三軒屋を再生した「上野桜木あたり」、明治23年創業の「谷中岡埜栄仙」、「旧吉田谷酒店」を見て上野へ向かう。2025年に創建400年を迎える「寛永寺」では、創建記念として「根本中堂」の天井に初めて天井絵が奉納されます。境内の徳川歴代将軍15人のうち6人が眠る「徳川家霊廟」を外から見学しました。

寛永寺根本中堂

国際子ども図書館へ向かう
最後に、明治時代に「帝国図書館」として建てられ、2002年に「国際子ども図書館」として全面開館された建物を見学しました。明治・昭和・平成の三つの時代に造られた建物が一体となり、貴重な建築遺産を保存利用しながら、新しい機能と空間を合わせもつ図書館として再生されました。この建物は現在、東京都の「歴史的建造物」に選定されています。明治時代のシャンデリア、元貴賓室の寄せ木細工の床や天井の鏝絵(こてえ)や柱など、帝国図書館として創建された当時を知ることができました。

国際子ども図書館
(文と写真: 田邊 博仁)
昔ながらの雰囲気を残した谷中・根津・千駄木・上野界隈を見て歩きました。特に印象に残ったのは、戦火や地震の被害を免れた通りにあるいわゆる「レトロ建物」でした。その多くが、今でもさまざまな方の努力で大切に残り、リノベーションされ、現役として生まれ変わっています。外観は昔の良き風情を残しながら、内部の雰囲気は現代風という店舗は「そこ」にマッチしていて、人気があるのもわかります。その中で気になった建物をいくつか紹介します。
最初は根津の「はん亭」です。1917年(大正6年)建築の木造三階建てを改築工事、串揚げ屋として営業しています。1999年(平成11年)有形登録文化財に登録されました。ここの面白いところは道路拡張時にセットバックした箇所を切断し、ガラス張りにしてさらにそこに鉄の矢来を施し、断面が通りから見えるようにしているところです。

串揚げやはん亭
しかし裏の路地から見ると、三階建ての木造建築がしっかりと残っており、現代と昔が外観で共存している建築になっているのがおしゃれです。
根津では他にレトロな建物として古い石蔵を利用したうどん屋、「宮の湯」という銭湯をリノベしたカフェや「束子(たわし)屋」なども、昔の面影を残しながら中は綺麗に改築されていて、粋でおしゃれな作りです。ここも路地にあり、地元に溶け込んでいました。

谷中ビアホール
上野に向かう途中、上野桜木あたりの「谷中ビアホール」、パン屋や日本初の塩とオリーブオイルの専門店が、木造二階に店舗を開いておりました。外観は昔の家屋ですが、その良さがしっかりと残っていて、どの店舗も外国人観光客含め多くの人で賑わっていました。
地元の人が利用している昔からの路地や建物が今でも残り、タイムスリップした錯覚すら覚えながらも、生活の中身は今の時代になっている、そんな「ここでしか見られない場所」を堪能した1日でした。
(文と写真:太田 義博)
江戸の町割りを残す根津と、
古民家リノベーションの谷中の今を歩く
11 月7日(土) 天気:快晴 参加者:13名
根津は、根津神社の門前町として栄え、庶民のまちとして賑わってきました。江戸時代の町割りを継承している路地、木造の建物や軒先などに溢れる緑など、むかしの古き良き佇まいを残し、懐かしさを感じさせます。歩いていてホッとする空間です。

元藍染川(区境)の路地

路地のゲストハウス

古民家の「花木屋」

三軒長屋の古民家店舗
また、根津には古民家を改築した建物が多い。大正初期の木造三階建て建物を改築した「はん亭」、明治の古いレンガ造りの蔵を改装した「うどん釜竹」、また、緑に囲まれた路地のゲストハウス、「花木屋」や三軒長屋の古民家店舗、廃業した銭湯をリニューアルした「SENTO」などを見て歩きました。

古い蔵を保存「うどん釜竹」

銭湯を再整備した「SENTO」
次に、不忍通りを渡り、大正8年に建てられ、関東大震災でも東京大空襲でも焼けなかった根津教会、根津遊郭の跡地のモニュメントを見て、根津神社へ向かいました。
根津神社の創建は1706年。当時の建物は現存して、修復作業が行われた極彩色の美しい楼門などは見事です。青空には大イチョウが鮮やかでした。

日本基督教団根津教会

極彩色の桜門

境内の鮮やかなイチョウの木

根津神社の桜門をバックに、本日の参加者のみなさま
再び不忍通りを渡り、へび道、よみせ通りをぶらぶら歩き、谷中ぎんざ界隈で昼食です。

谷中ぎんざ(写真:宇佐美)
午後は、築約100年の日本家屋をリノベーションした建物(「錻力屋」、「銅菊」、「小倉屋質店」)、江戸時代の「観音寺築地塀」や「絵馬堂」、「のんびりや」、古書「鮫の歯」などを見ながら、谷中霊園へ。参道の明治からの老舗花屋「花重」に「花重谷中茶屋」がオープン(2023年)していました。

絵馬堂(休業中)

古書「鮫の歯」
そして、昭和13年に建てられた三軒屋を再生した「上野桜木あたり」、明治23年創業の「谷中岡埜栄仙」、「旧吉田谷酒店」を見て上野へ向かう。2025年に創建400年を迎える「寛永寺」では、創建記念として「根本中堂」の天井に初めて天井絵が奉納されます。境内の徳川歴代将軍15人のうち6人が眠る「徳川家霊廟」を外から見学しました。

寛永寺根本中堂

国際子ども図書館へ向かう
最後に、明治時代に「帝国図書館」として建てられ、2002年に「国際子ども図書館」として全面開館された建物を見学しました。明治・昭和・平成の三つの時代に造られた建物が一体となり、貴重な建築遺産を保存利用しながら、新しい機能と空間を合わせもつ図書館として再生されました。この建物は現在、東京都の「歴史的建造物」に選定されています。明治時代のシャンデリア、元貴賓室の寄せ木細工の床や天井の鏝絵(こてえ)や柱など、帝国図書館として創建された当時を知ることができました。

国際子ども図書館
(文と写真: 田邊 博仁)
昔ながらの路地や建物が残り、中身は”今“という粋なしゃれっ気
昔ながらの雰囲気を残した谷中・根津・千駄木・上野界隈を見て歩きました。特に印象に残ったのは、戦火や地震の被害を免れた通りにあるいわゆる「レトロ建物」でした。その多くが、今でもさまざまな方の努力で大切に残り、リノベーションされ、現役として生まれ変わっています。外観は昔の良き風情を残しながら、内部の雰囲気は現代風という店舗は「そこ」にマッチしていて、人気があるのもわかります。その中で気になった建物をいくつか紹介します。
最初は根津の「はん亭」です。1917年(大正6年)建築の木造三階建てを改築工事、串揚げ屋として営業しています。1999年(平成11年)有形登録文化財に登録されました。ここの面白いところは道路拡張時にセットバックした箇所を切断し、ガラス張りにしてさらにそこに鉄の矢来を施し、断面が通りから見えるようにしているところです。

串揚げやはん亭
しかし裏の路地から見ると、三階建ての木造建築がしっかりと残っており、現代と昔が外観で共存している建築になっているのがおしゃれです。
根津では他にレトロな建物として古い石蔵を利用したうどん屋、「宮の湯」という銭湯をリノベしたカフェや「束子(たわし)屋」なども、昔の面影を残しながら中は綺麗に改築されていて、粋でおしゃれな作りです。ここも路地にあり、地元に溶け込んでいました。

谷中ビアホール
上野に向かう途中、上野桜木あたりの「谷中ビアホール」、パン屋や日本初の塩とオリーブオイルの専門店が、木造二階に店舗を開いておりました。外観は昔の家屋ですが、その良さがしっかりと残っていて、どの店舗も外国人観光客含め多くの人で賑わっていました。
地元の人が利用している昔からの路地や建物が今でも残り、タイムスリップした錯覚すら覚えながらも、生活の中身は今の時代になっている、そんな「ここでしか見られない場所」を堪能した1日でした。
(文と写真:太田 義博)
他の町のフットパスを見てみよう 福島市信夫山
2024.10.26
[ 講師:みどりのゆび 神谷 由紀子 ]
信夫山150周年記念フットパスに参加してきました。
10月26日(土)~27日(日) 天気:晴 参加者:5名
今、東北地方ではフットパスを有効利用して地域活性化に勢いをつけている地域が増えています。しかも地域自治体を上手に巻き込み、資金や基盤を確立して本格的なまちづくりに貢献している傾向が顕著です。
その例の一つが10月27日に福島市のシンボルである信夫山公園開設150周年を記念して行われたフットパス事業です。
「NPO法人 ストリートふくしま」の山尾良平さんは福島市民のシンボルである「信夫山」にフットパスを作り、東日本大震災後、支援を受けるだけでなく福島市民自らの力で、ふるさと福島のまちを再生しようとしています。
信夫山はもともと観光地ではなく信仰の山であり、福島市の誕生からセットとなった地形と歴史の宝庫でもあります。信夫山の信夫という名前は、5,6世紀ごろから福島県が大和朝廷勢力の北限であった信夫国として認識されている由緒ある名前です。したがって信夫山には欽明天皇の后や皇子が都を追われ、六供という家臣たちと共に住み着いたとされる古い伝説もあるのです。太古から神聖な場所である信夫三山を有し、弘法大師伝説や山伏修験の修行場などで知られる信仰の山としてあがめられ、シンボルとされてきました。

弘法大師(空海)の座禅石

古峯神社

信夫山展望デッキ
このように多くの名所や景観の魅力あふれる山なのですが、それをどうやって広報して集客し、自分たちの誇りとして継承していくのかということで、山尾さんはフットパスの事業化を考えたのです。「今年は150周年なので信夫山のレガシーを作ろう」という市長の方針とも相まって、10月27日にはセレモニーが開催され、信夫山フットパス・マップの除幕式、そしてガイド20名、参加者87名のフットパス・ウォークが行われました。

木幡福島市長、浦部会長らとフットパス・マップ除幕式
(写真:山尾)


信夫山フットパスのスタッフと受付(写真:山尾)

信夫山フットパス・ガイドウォーク(写真:山尾)
今回は井上、新納、浅野、神谷、北浦の5名がその記念イベントに参加しました。イベント前日の26日から入り、”信夫山博士”と言われる第一人者浦部博さんを独占して特別ルートをご案内いただきました。27日当日も一番展望の良い烏ケ崎展望コースを回りました。帰りは女性3人で飯坂温泉までタクシーで行き、わざわざ飯電に乗って福島駅まで、信夫山から見た電車の実車をして大満足でした。

みどりのゆびのメンバーと(写真:山尾)

烏ケ崎展望デッキからの眺望

安達太良連邦と吾妻連峰
今回は、山尾さんのお城・信夫山ガイドセンターで、張り出した窓から阿武隈山系、安達太良連峰、吾妻連峰に囲まれた福島市内の超絶景を見ながらのおむすびと、スタッフの方が入れてくださった美味しいコーヒーの昼食をご馳走になり、印象に残りました。改めてフットパスの良さは人との交流がなければできない特別なおもてなしにあるのだと思いました。そして地元の方に友達特別待遇で案内していただく優しさがフットパスの”魔力”なんだなと、思い返したことでした。フットパスは楽しく癒しとなり、私たちの人生をサポートしてくれます。
(文と写真:神谷 由紀子)
令和5年10月、福島県西郷村で開催されたフットパス全国大会に参加し、福島県でもフットパスの火が燃えていることを実感しました。その4カ月前に信夫山から街づくりを行うNPO法人を引き継いだ私は、かなりの感動と影響を受けて帰ってきました。
まずは信夫山フットパス・マップ作りに取り掛かりました。町田・みどりのゆび発行のマップを参考に、イラストレーターを選定。ルートは信夫山研究58年の”信夫山博士”に依頼して作成をスタートしました。そこに信夫山公園開園150周年の追い風が吹いて、福島市が応援してくれることになりました。
市の協力も受け、フットパス案内人を募集・育成、23名の案内人を確保。参加者募集は80名に対し福島市内外から100名の申込がありました。そして、昨年10月27日に市主催の信夫山公園150周年記念式典で信夫山フットパス・マップ4種類を発表。87名の参加者で記念ウォークを開催することができました。
記念ウォークには東京・町田から神谷さん、山形・長井から浅野さん、福島・西郷から北浦さんにも参加いただきました。ありがとうございました。こうして何とか無事に終了。思えば昨年3月にマップ作りに着手、8か月で信夫山フットパス実施に至りました。当初、私の中ではマップを10月に発表するだけの予定でしたが、神谷さんの神!?のお導きにより、白いキャンバスに道を描くようにスイスイと事が運んだことが、ホント不思議です。というか感謝です!
今後は、案内人という強い味方もできましたので、信夫山フットパスを更に発展させていきたいと考えています。応援してください。

式典で山尾さんがフットパスについて説明(写真:神谷)
(文:NPO法人 ストリートふくしま理事長
山尾 良平)
*特定非営利活動法人 ストリートふくしま
https://www.shinobuyama.com/
信夫山150周年記念フットパスに参加してきました。
10月26日(土)~27日(日) 天気:晴 参加者:5名
今、東北地方ではフットパスを有効利用して地域活性化に勢いをつけている地域が増えています。しかも地域自治体を上手に巻き込み、資金や基盤を確立して本格的なまちづくりに貢献している傾向が顕著です。
その例の一つが10月27日に福島市のシンボルである信夫山公園開設150周年を記念して行われたフットパス事業です。
「NPO法人 ストリートふくしま」の山尾良平さんは福島市民のシンボルである「信夫山」にフットパスを作り、東日本大震災後、支援を受けるだけでなく福島市民自らの力で、ふるさと福島のまちを再生しようとしています。
信夫山はもともと観光地ではなく信仰の山であり、福島市の誕生からセットとなった地形と歴史の宝庫でもあります。信夫山の信夫という名前は、5,6世紀ごろから福島県が大和朝廷勢力の北限であった信夫国として認識されている由緒ある名前です。したがって信夫山には欽明天皇の后や皇子が都を追われ、六供という家臣たちと共に住み着いたとされる古い伝説もあるのです。太古から神聖な場所である信夫三山を有し、弘法大師伝説や山伏修験の修行場などで知られる信仰の山としてあがめられ、シンボルとされてきました。

弘法大師(空海)の座禅石

古峯神社

信夫山展望デッキ
このように多くの名所や景観の魅力あふれる山なのですが、それをどうやって広報して集客し、自分たちの誇りとして継承していくのかということで、山尾さんはフットパスの事業化を考えたのです。「今年は150周年なので信夫山のレガシーを作ろう」という市長の方針とも相まって、10月27日にはセレモニーが開催され、信夫山フットパス・マップの除幕式、そしてガイド20名、参加者87名のフットパス・ウォークが行われました。

木幡福島市長、浦部会長らとフットパス・マップ除幕式
(写真:山尾)


信夫山フットパスのスタッフと受付(写真:山尾)

信夫山フットパス・ガイドウォーク(写真:山尾)
今回は井上、新納、浅野、神谷、北浦の5名がその記念イベントに参加しました。イベント前日の26日から入り、”信夫山博士”と言われる第一人者浦部博さんを独占して特別ルートをご案内いただきました。27日当日も一番展望の良い烏ケ崎展望コースを回りました。帰りは女性3人で飯坂温泉までタクシーで行き、わざわざ飯電に乗って福島駅まで、信夫山から見た電車の実車をして大満足でした。

みどりのゆびのメンバーと(写真:山尾)

烏ケ崎展望デッキからの眺望

安達太良連邦と吾妻連峰
今回は、山尾さんのお城・信夫山ガイドセンターで、張り出した窓から阿武隈山系、安達太良連峰、吾妻連峰に囲まれた福島市内の超絶景を見ながらのおむすびと、スタッフの方が入れてくださった美味しいコーヒーの昼食をご馳走になり、印象に残りました。改めてフットパスの良さは人との交流がなければできない特別なおもてなしにあるのだと思いました。そして地元の方に友達特別待遇で案内していただく優しさがフットパスの”魔力”なんだなと、思い返したことでした。フットパスは楽しく癒しとなり、私たちの人生をサポートしてくれます。
(文と写真:神谷 由紀子)
信夫山フットパス始動!
令和5年10月、福島県西郷村で開催されたフットパス全国大会に参加し、福島県でもフットパスの火が燃えていることを実感しました。その4カ月前に信夫山から街づくりを行うNPO法人を引き継いだ私は、かなりの感動と影響を受けて帰ってきました。
まずは信夫山フットパス・マップ作りに取り掛かりました。町田・みどりのゆび発行のマップを参考に、イラストレーターを選定。ルートは信夫山研究58年の”信夫山博士”に依頼して作成をスタートしました。そこに信夫山公園開園150周年の追い風が吹いて、福島市が応援してくれることになりました。
市の協力も受け、フットパス案内人を募集・育成、23名の案内人を確保。参加者募集は80名に対し福島市内外から100名の申込がありました。そして、昨年10月27日に市主催の信夫山公園150周年記念式典で信夫山フットパス・マップ4種類を発表。87名の参加者で記念ウォークを開催することができました。
記念ウォークには東京・町田から神谷さん、山形・長井から浅野さん、福島・西郷から北浦さんにも参加いただきました。ありがとうございました。こうして何とか無事に終了。思えば昨年3月にマップ作りに着手、8か月で信夫山フットパス実施に至りました。当初、私の中ではマップを10月に発表するだけの予定でしたが、神谷さんの神!?のお導きにより、白いキャンバスに道を描くようにスイスイと事が運んだことが、ホント不思議です。というか感謝です!
今後は、案内人という強い味方もできましたので、信夫山フットパスを更に発展させていきたいと考えています。応援してください。

式典で山尾さんがフットパスについて説明(写真:神谷)
(文:NPO法人 ストリートふくしま理事長
山尾 良平)
*特定非営利活動法人 ストリートふくしま
https://www.shinobuyama.com/
フットパス専門家講座 「横浜自然観察の森」を訪ねて
2024.10.06
[ 講師:日本植物友の会会長 山田 隆彦 ]
自然の異変を感じさせる消えた植物たち
10月6日(日) 天気:曇り 参加者:14名
「横浜自然観察の森」は、「多摩・三浦丘陵群」の一部で、横浜市最大の緑地。1986年に日本で初めての自然公園として開園した。
この観察会で見ていただきたかった植物の内、ネナシカズラの群落とイヌセンブリに出合えなかったのは残念なことであった。
寄生植物のネナシカズラは、ピクニック広場のクズやセイタカアワダチソウにとりついて覆いかぶさっていた。2023年10月のことである。ところが今年(2024年)の10月には見られず、突然に消えてしまって1株も確認できなかったのである。理由はわからない。どこかに残っているのではと探し回ったが見つからない。ここを管理している自然観察センターの方にも尋ねたが、どこにもないという。
イヌセンブリは、センブリと違って、葉っぱを噛んでも辛くない。薬用には使われない。神奈川県では、現在、この地でしか見られない。絶滅危惧種に指定されている。これも消えてしまったのか、センターの方が探し回った足跡が残っていたが、1本も見つからなかったという。なにか自然に異変が起きているのではないかと危惧する。

ネナシカズラ2023.10.13
スダジイブナ科
スダジイの実(堅果)がわんさと付いていた。10日後に訪ねたら実っていて、ドングリは今にも下に落ちそうになっていた。この実は生でも食べられる。本州から九州まで分布して、日本の暖帯林の最重要樹種の一つで、暖地の森を代表する木である。かつては薪炭林として利用していたが、今はシイタケ栽培のほだ木に利用されている。
スダジイの森では、花期になるとくすんだ薄い黄色で一帯を彩り、独特の香りを漂わせる。人によっては不快な臭いでもある。

スダジイ2024.10.6

スダジイ2024.10.16(10日後)
ママコノシリヌグイタデ科
すごい名前である。漢字では、「継子の尻拭い」と書く。茎や葉には、刺がいっぱい生えている。これで継子のお尻をふくという。ひどい継母である。ピンク色に見えているのはがくで、花弁はない。

ママコノシリヌグイ2024.10.6
ツルマメマメ科
野原や道端にふつうに見られるつる植物で、淡紫色の花を付ける。ダイズの原種といわれ、学名(世界共通名)は、グリキネ・マックス・ソヤといい、ソヤは醤油syoyuに由来している。

ツルマメ2024.10.6

ガマズミガマズミ科
ガマズミの果実が赤く実っており、一際目立った。赤い色の果実は主に鳥に食べてもらって種子を遠くに運んでもらうため、目立った色をしている。この赤い実の中に種が1個入っている。名前は、実をかむと酸っぱいので、「かむ酢実」から転化してガマズミという説や、ズミは、この果実を使って衣類をすり染めした「染め」の転化という説もある。
ガマズミ2024.10.6
目的とした植物は見られなかったが、ススキの根元に寄生植物のナンバンギセルを見つけ、帰りのバス停近くでは、午後3時になると咲きだす熱帯アメリカ原産の帰化植物、ハゼラン(別名サンジソウ)の赤い花を見ながら観察会を終えた。

ハゼラン2024.10.6
(文と写真:山田 隆彦)
秋の草花に親しんだ一日で、森の歩き方を新たに発見
9月に入っても猛暑が収まらず、秋の訪れが待ち遠しくなっていたのですが、ようやく秋の気配が感じられるようになった10月最初の日曜日、山田先生のご案内により、秋の草花に親しむ一日を過ごすことができました。
「横浜自然観察の森」は、雑木林・草地・水辺など、多様な自然に恵まれ、これまでに多くの野鳥をはじめ、約3,500種類もの動植物が確認されているそうです。
山田先生を先頭に、鬱蒼とした森に整備されたネイチャートレイルを進みます。参加者の明るい声が響き、会話も弾みます。

山田先生による植物解説

自然植生豊かなトレイルを歩く
山田先生のご案内で森の小径を歩くと、次々に可憐な草花が見つかります。独りで漠然と歩いているときには、たくさんの森の宝物を見落としていたことに気づかされます。森の歩き方の新たな発見でもありました。
煎じて飲むとすぐに薬効(胃腸病)が現れるゲンノショウコの他、ママコノシリヌグイ(継子の尻拭い)の名前の由来なども聞きながら、楽しく学ぶことができました。

シロヨメナ

ゲンノショウコ
(文と写真:宇佐美 均)
自然の異変を感じさせる消えた植物たち
10月6日(日) 天気:曇り 参加者:14名
「横浜自然観察の森」は、「多摩・三浦丘陵群」の一部で、横浜市最大の緑地。1986年に日本で初めての自然公園として開園した。
この観察会で見ていただきたかった植物の内、ネナシカズラの群落とイヌセンブリに出合えなかったのは残念なことであった。
寄生植物のネナシカズラは、ピクニック広場のクズやセイタカアワダチソウにとりついて覆いかぶさっていた。2023年10月のことである。ところが今年(2024年)の10月には見られず、突然に消えてしまって1株も確認できなかったのである。理由はわからない。どこかに残っているのではと探し回ったが見つからない。ここを管理している自然観察センターの方にも尋ねたが、どこにもないという。
イヌセンブリは、センブリと違って、葉っぱを噛んでも辛くない。薬用には使われない。神奈川県では、現在、この地でしか見られない。絶滅危惧種に指定されている。これも消えてしまったのか、センターの方が探し回った足跡が残っていたが、1本も見つからなかったという。なにか自然に異変が起きているのではないかと危惧する。

ネナシカズラ2023.10.13
スダジイブナ科
スダジイの実(堅果)がわんさと付いていた。10日後に訪ねたら実っていて、ドングリは今にも下に落ちそうになっていた。この実は生でも食べられる。本州から九州まで分布して、日本の暖帯林の最重要樹種の一つで、暖地の森を代表する木である。かつては薪炭林として利用していたが、今はシイタケ栽培のほだ木に利用されている。
スダジイの森では、花期になるとくすんだ薄い黄色で一帯を彩り、独特の香りを漂わせる。人によっては不快な臭いでもある。

スダジイ2024.10.6

スダジイ2024.10.16(10日後)
ママコノシリヌグイタデ科
すごい名前である。漢字では、「継子の尻拭い」と書く。茎や葉には、刺がいっぱい生えている。これで継子のお尻をふくという。ひどい継母である。ピンク色に見えているのはがくで、花弁はない。

ママコノシリヌグイ2024.10.6
ツルマメマメ科
野原や道端にふつうに見られるつる植物で、淡紫色の花を付ける。ダイズの原種といわれ、学名(世界共通名)は、グリキネ・マックス・ソヤといい、ソヤは醤油syoyuに由来している。

ツルマメ2024.10.6

ガマズミガマズミ科
ガマズミの果実が赤く実っており、一際目立った。赤い色の果実は主に鳥に食べてもらって種子を遠くに運んでもらうため、目立った色をしている。この赤い実の中に種が1個入っている。名前は、実をかむと酸っぱいので、「かむ酢実」から転化してガマズミという説や、ズミは、この果実を使って衣類をすり染めした「染め」の転化という説もある。
ガマズミ2024.10.6
目的とした植物は見られなかったが、ススキの根元に寄生植物のナンバンギセルを見つけ、帰りのバス停近くでは、午後3時になると咲きだす熱帯アメリカ原産の帰化植物、ハゼラン(別名サンジソウ)の赤い花を見ながら観察会を終えた。

ハゼラン2024.10.6
(文と写真:山田 隆彦)
秋の草花に親しんだ一日で、森の歩き方を新たに発見
9月に入っても猛暑が収まらず、秋の訪れが待ち遠しくなっていたのですが、ようやく秋の気配が感じられるようになった10月最初の日曜日、山田先生のご案内により、秋の草花に親しむ一日を過ごすことができました。
「横浜自然観察の森」は、雑木林・草地・水辺など、多様な自然に恵まれ、これまでに多くの野鳥をはじめ、約3,500種類もの動植物が確認されているそうです。
山田先生を先頭に、鬱蒼とした森に整備されたネイチャートレイルを進みます。参加者の明るい声が響き、会話も弾みます。

山田先生による植物解説

自然植生豊かなトレイルを歩く
山田先生のご案内で森の小径を歩くと、次々に可憐な草花が見つかります。独りで漠然と歩いているときには、たくさんの森の宝物を見落としていたことに気づかされます。森の歩き方の新たな発見でもありました。
煎じて飲むとすぐに薬効(胃腸病)が現れるゲンノショウコの他、ママコノシリヌグイ(継子の尻拭い)の名前の由来なども聞きながら、楽しく学ぶことができました。

シロヨメナ

ゲンノショウコ
(文と写真:宇佐美 均)
他のまちのフットパスをみてみよう 奥多摩駅の周辺を歩く
2024.07.06
[ 講師: 小林 道正]
ダム建設と石灰石運搬でできた 地域の残照の魅力
7月6日(土) 天気:晴のち曇 参加者:13名
JR奥多摩駅は標高343mの東京都で最も高いところにある駅で、山小屋風の駅舎が人気です。土日は多くの登山者で賑わっています。

山小屋風の奥多摩駅舎
「奥多摩駅」は昭和19年にセメントの原料となる石灰石を運搬する鉄道に「氷川駅」という名称で開業しました。戦後になって東京都民の飲料水を確保する「小河内ダム」を建設するために、資材運搬の拠点として大きな役割を果たしました。
<コース紹介>①JR奥多摩駅⇒②奥多摩ビジターセンター⇒③奥多摩工業曳鉄線⇒④奥氷川神社・多摩川の河原(昼食)⇒⑤東京都水道局小河内線(廃線跡)⇒⑥奥多摩むかし道⇒①JR奥多摩駅
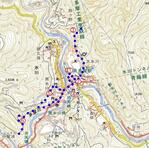
コースMAP
奥多摩は『東京の屋根』とよばれるほどの山地で、雲取山(2017m)を頂点にして急峻な山と深い谷が集まっています。地質は古生代と中生代の泥岩や砂岩、チャートなどの他に石灰岩が多く分布しています。
歴史的には『甲州裏街道』とよばれる武蔵国と甲斐国を結ぶ旧青梅街道が通り、交易路として人々が往来していました。
<①JR奥多摩駅から②奥多摩ビジターセンターへ>
「奥多摩ビジターセンター」は自然や文化について分かりやすく展示し解説してくれる施設です。最近は熊の目撃情報や被害が多発しているために、ツキノワグマの生態や習性について剥製や骨格標本を使って解説しています。
<③奥多摩工業の曳鉄線(ひきがねせん)>
「奥多摩工業」は石灰石を採石して運搬している会社です。石灰石はセメントの原料となる貴重な鉱物資源で、多くの建物や道路などを造り発展してきました。近年の石灰石は新しい素材として注目され、紙の原料、食品添加物、化粧品などに利用されているそうです。
「曳鉄線」は「えいてつせん」とか「ひきがねせん」と読まれています。トロッコをロープで繋ぎ線路の上をエンドレスで回している仕組みの鉄道で、スキー場のリフトのイメージです。昭和28年から現在も現役で稼働中です。
杉林の中に鉄橋とトンネルが見えてきました。残念ながら動いていませんでしたが、複線の線路の上にロープに繋がれたトロッコが4台停車していました。左側の線路に乗った2台には石灰石が乗せられ、右側は空でした。

石灰石を運ぶ無人トロッコ
石灰石の採石場は5km先にあり、トンネルと鉄橋で結んで線路を敷き、無人のトロッコを使って石灰石を運搬しています。70年前は空中を通るリフト方式でしたが、需要が増えて運搬量を増やすためにトンネルを掘って地中を通すようにしたそうです。運搬量の増加だけでなく、費用と安全性も格段に向上したそうです。
トロッコ1台の積載量は3t。径32mmのロープで276台のトロッコを36m間隔で繋いでいます。動くスピードは秒速2mとのことでした。
<④奥氷川神社>
さいたま市の「氷川神社」、所沢市の「中氷川神社」とともに『武蔵三氷川』として有名です。
『御神体』の『三本杉』があります。お昼のお弁当は多摩川と日原川が合流する河原で美味しくいただきました。
<⑤⑥東京都水道局小河内線の軌道跡>
「小河内ダム」を建設するために昭和27~32年に使われていた資材輸送用の貨物線跡です。ダム完成後は西武鉄道が観光列車を走らせる計画だったそうです。しかし、採算性や安全性が確保できなかったのか実現することはありませんでした。
線路跡に沿って『奥多摩むかし道』があり、歩くことができます。旧青梅街道です。
JR奥多摩駅に戻ってビールで乾杯しました。

貨物線跡のトンネルの上で手を振るみなさま

奥多摩駅でビールで乾杯!
(文と写真:小林 道正)
石灰石を運ぶトロッコと、トンネルや 線路跡が深い杉林に包まれて
奥多摩駅は『関東の駅百選』の一つで、昭和19年に開業した海抜343mに位置する木造建築。趣のある駅舎です。駅舎のあちこちにツバメの巣があり、ツバメたちも大勢の登山客や観光客を迎えてくれていました。
先ずは「奥多摩ビジターセンター」で奥多摩の成立ち、自然や熊の生態などを受講。奥多摩の初歩的な知識を享受することができました。
奥多摩駅周辺は急峻な山々で、その中腹まで宅地化されており、アクセスの道路も急勾配です。降雪もあることから、コンクリート舗装には溝が刻まれており、冬期の運転は厳しいものと感じられました。
最初の目的地は「石灰石を採掘精製している奥多摩工業㈱」で、氷川鉱山で採掘した石灰石を運搬する森の中を5km走るトロッコ線路(かつては276台を32mmのワイヤーで連結)と鉄橋、トンネルを観ることができました。
午後からの「奥多摩むかし道」は旧青梅街道で全長は奥多摩駅から奥多摩湖までの10kmですが、今回は槐木(サイカチの木)までのアップダウンの約2kmのコース。並行して小河内ダム建設で資材を輸送した貨物線のレールやトンネル・鉄橋跡を間近で観られ、トンネル内を歩くこともできました。最終地「槐木」のサイカチノの木は樹高15m、幹回り3mの大きなサヤがぶら下がることでも知られる古木で、土地の名称にもなっています。
多摩川の源流と急峻な山を背景に、産業遺産や土木遺産に触れながらの楽しい奥多摩駅周辺のフットパスでした。
奥多摩駅2階のカフェ「ポートおくたま」ではクラフトビールが飲めます。最後に「参加された13名の皆さんお疲れさんでした」で乾杯!
ほどよい疲れを感じながらそれぞれ帰路に着きました。
(文:浅野 敏明)

貨物線跡のトンネルから出てきたみなさま(写真:田邊)
ダム建設と石灰石運搬でできた 地域の残照の魅力
7月6日(土) 天気:晴のち曇 参加者:13名
JR奥多摩駅は標高343mの東京都で最も高いところにある駅で、山小屋風の駅舎が人気です。土日は多くの登山者で賑わっています。

山小屋風の奥多摩駅舎
「奥多摩駅」は昭和19年にセメントの原料となる石灰石を運搬する鉄道に「氷川駅」という名称で開業しました。戦後になって東京都民の飲料水を確保する「小河内ダム」を建設するために、資材運搬の拠点として大きな役割を果たしました。
<コース紹介>①JR奥多摩駅⇒②奥多摩ビジターセンター⇒③奥多摩工業曳鉄線⇒④奥氷川神社・多摩川の河原(昼食)⇒⑤東京都水道局小河内線(廃線跡)⇒⑥奥多摩むかし道⇒①JR奥多摩駅
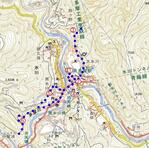
コースMAP
奥多摩は『東京の屋根』とよばれるほどの山地で、雲取山(2017m)を頂点にして急峻な山と深い谷が集まっています。地質は古生代と中生代の泥岩や砂岩、チャートなどの他に石灰岩が多く分布しています。
歴史的には『甲州裏街道』とよばれる武蔵国と甲斐国を結ぶ旧青梅街道が通り、交易路として人々が往来していました。
<①JR奥多摩駅から②奥多摩ビジターセンターへ>
「奥多摩ビジターセンター」は自然や文化について分かりやすく展示し解説してくれる施設です。最近は熊の目撃情報や被害が多発しているために、ツキノワグマの生態や習性について剥製や骨格標本を使って解説しています。
<③奥多摩工業の曳鉄線(ひきがねせん)>
「奥多摩工業」は石灰石を採石して運搬している会社です。石灰石はセメントの原料となる貴重な鉱物資源で、多くの建物や道路などを造り発展してきました。近年の石灰石は新しい素材として注目され、紙の原料、食品添加物、化粧品などに利用されているそうです。
「曳鉄線」は「えいてつせん」とか「ひきがねせん」と読まれています。トロッコをロープで繋ぎ線路の上をエンドレスで回している仕組みの鉄道で、スキー場のリフトのイメージです。昭和28年から現在も現役で稼働中です。
杉林の中に鉄橋とトンネルが見えてきました。残念ながら動いていませんでしたが、複線の線路の上にロープに繋がれたトロッコが4台停車していました。左側の線路に乗った2台には石灰石が乗せられ、右側は空でした。

石灰石を運ぶ無人トロッコ
石灰石の採石場は5km先にあり、トンネルと鉄橋で結んで線路を敷き、無人のトロッコを使って石灰石を運搬しています。70年前は空中を通るリフト方式でしたが、需要が増えて運搬量を増やすためにトンネルを掘って地中を通すようにしたそうです。運搬量の増加だけでなく、費用と安全性も格段に向上したそうです。
トロッコ1台の積載量は3t。径32mmのロープで276台のトロッコを36m間隔で繋いでいます。動くスピードは秒速2mとのことでした。
<④奥氷川神社>
さいたま市の「氷川神社」、所沢市の「中氷川神社」とともに『武蔵三氷川』として有名です。
『御神体』の『三本杉』があります。お昼のお弁当は多摩川と日原川が合流する河原で美味しくいただきました。
<⑤⑥東京都水道局小河内線の軌道跡>
「小河内ダム」を建設するために昭和27~32年に使われていた資材輸送用の貨物線跡です。ダム完成後は西武鉄道が観光列車を走らせる計画だったそうです。しかし、採算性や安全性が確保できなかったのか実現することはありませんでした。
線路跡に沿って『奥多摩むかし道』があり、歩くことができます。旧青梅街道です。
JR奥多摩駅に戻ってビールで乾杯しました。

貨物線跡のトンネルの上で手を振るみなさま

奥多摩駅でビールで乾杯!
(文と写真:小林 道正)
石灰石を運ぶトロッコと、トンネルや 線路跡が深い杉林に包まれて
奥多摩駅は『関東の駅百選』の一つで、昭和19年に開業した海抜343mに位置する木造建築。趣のある駅舎です。駅舎のあちこちにツバメの巣があり、ツバメたちも大勢の登山客や観光客を迎えてくれていました。
先ずは「奥多摩ビジターセンター」で奥多摩の成立ち、自然や熊の生態などを受講。奥多摩の初歩的な知識を享受することができました。
奥多摩駅周辺は急峻な山々で、その中腹まで宅地化されており、アクセスの道路も急勾配です。降雪もあることから、コンクリート舗装には溝が刻まれており、冬期の運転は厳しいものと感じられました。
最初の目的地は「石灰石を採掘精製している奥多摩工業㈱」で、氷川鉱山で採掘した石灰石を運搬する森の中を5km走るトロッコ線路(かつては276台を32mmのワイヤーで連結)と鉄橋、トンネルを観ることができました。
午後からの「奥多摩むかし道」は旧青梅街道で全長は奥多摩駅から奥多摩湖までの10kmですが、今回は槐木(サイカチの木)までのアップダウンの約2kmのコース。並行して小河内ダム建設で資材を輸送した貨物線のレールやトンネル・鉄橋跡を間近で観られ、トンネル内を歩くこともできました。最終地「槐木」のサイカチノの木は樹高15m、幹回り3mの大きなサヤがぶら下がることでも知られる古木で、土地の名称にもなっています。
多摩川の源流と急峻な山を背景に、産業遺産や土木遺産に触れながらの楽しい奥多摩駅周辺のフットパスでした。
奥多摩駅2階のカフェ「ポートおくたま」ではクラフトビールが飲めます。最後に「参加された13名の皆さんお疲れさんでした」で乾杯!
ほどよい疲れを感じながらそれぞれ帰路に着きました。
(文:浅野 敏明)

貨物線跡のトンネルから出てきたみなさま(写真:田邊)
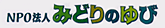
 2024.11.09 23:29
|
2024.11.09 23:29
| 


